ニュース
第5回洪水管理国際会議(ICFM5)を開催
9月27~29日、ICHARM ICFM5事務局の主催で第5回洪水管理国際会議(ICFM5)が開催されました。会議には、世界41カ国から450 名以上の参加がありました。
発表論文要旨投稿の呼びかけや、オンライン参加登録は予想以上の成果を上げました。最終的に、投稿は事務局が設定したトピック分野を網羅し合計417件、参加者数も3日間で、国内200余名、海外からも250名を超え、大変な盛会となりました。ICFM5国際科学委員会はすべての要旨を審査、その結果256件が、ふたつの全体会合、8つの特別セッション、26の分科会、そしてポスター・ブースセッションで発表されました。また、会議1日目の国際フォーラムでは、上級専門家を招いての講演も行われました。
ICFM5第1日目は、27日、国連大学において、竹内邦良ICHARMセンター長の開会の辞によって始まりました。開会式では、Michel Jarraud WMO事務局長、Soon-tak Lee UNESCO-IHP議長、武内和彦国連大学副学長、そして、Slobodan Simonovic ICFM特別委員会議長からも祝辞をいただきました。

開会式後、「洪水予報早期警報」、「豪雨による洪水、地すべり、土石流」をテーマに、ふたつの全体会合が行われ、午後には、国土交通省等による「巨大水災害に関する国際フォーラム」が開催されました。
国際フォーラムの開催趣旨は、本年の東日本大震災を受け、広い見地から各国の経験と教訓を共有し、巨大水災害に備えようとするものです。基調講演やハイレベルパネルディスカッション(水と災害に関する有識者会合)などを通じて行われた議論は、ICFM5宣言案に反映されました。皇太子殿下のご聴講をはじめ、パキスタンのChangez Khan Jamali科学技術大臣、フィリピンのRogelio Singson公共事業交通長官を含む外国政府高官の参加もいただきました。
秋葉原UDXで行われた第2、3日目には、特別セッション、分科会、ポスターセッション、展示会などがありました。会議参加者には、論文要旨300件を収めた要旨集と、IFIの活動に貢献する主旨でICHARMが企画した報告書「大規模洪水レポート」が配布されました。最終日にはICFM5宣言案を発表、次回ICFM6のホスト国としてブラジルを指名し、29日に閉会しました。
ICFM5テクニカルプログラムの概要
A)大規模水災害に関する国際フォーラム、全体会議(口頭発表14件):
- 大規模水災害に関する国際フォーラム(主催:国土交通省、 WMO、 UNESCO、UNU、水と災害に関するハイレベル専門家パネル(HLEP/UNSGAB) 後援:内閣府、外務省、財務省)
- 早期洪水予警報システム(企画:WMO、UNESCO through IFI )
集中豪雨に起因する洪水、地すべり、土石流(主催:IWHR、IMHE-China Academy of Science、University of Leeds)

B)特別セッション(口頭発表34件):
- 日本、オランダ、イギリス、アメリカ各国で利用されている洪水リスク管理手法(主催: USACE、国土交通省、Rijkswaterstaat、Environment Agency)
- 気候変動適応への現実的な方策(主催: ICIWaRM)
- 洪水管理関連プログラム実施10年を迎えて(主催:WMO、GWP)
- 洪水管理分野の教育と能力開発(主催:UNESCO-IHE、ICHARM)
- 洪水に強いコミュニティーの構築(主催:UNU-ISP、JICA)
- 洪水モデリングの水理における進歩と新たな方向性(主催:IAHR-IFI)
- 洪水リスク管理手法とその適用例(HR Wallingford、Deltares)
- 洪水防災:ヨーロッパで最近実施された研究プロジェクトの成果としての学際的手法(UFZ-Germany、Middlesex University)

C)分科会(口頭発表156件):
Topic 1:洪水リスク管理(防止、緩和、適応)48件
Topic 2:洪水災害管理(防災、緊急対応、復旧)30件
Topic 3:洪水予警報システム40件
Topic 4:異なる気候条件下、地理区分での洪水管理20件
Topic 5:分野横断的課題他18件

D)ポスターセッション48件
E)展示15件
WMO、NCDR-Taiwan、JWA、RFC、Tokyo University、IDI、ICHARM、Forum8、Pacific Consultants、Takuwa、YSI Nanotech、Yachiyo Eng.、Kokusai Kogyo、 Obayashi-Gumi、PASCO Corporation
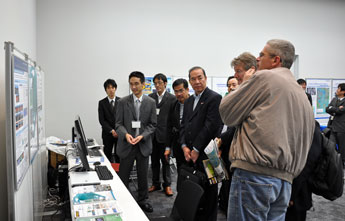
F)サイドイベント
- ICFM特別委員会 9月28日
- パキスタン科学技術大臣、フィリピン公共事業道路長官とのIDI主催ミーティング 9月28日
- IAHR-IFI組織内会議 9月28日
- 国際洪水イニシアチブ諮問・管理委員会会議 9月29日
G)テクニカルツアー
荒川、鶴見川両河川の洪水防止関連施設を見学するツアーを行い、約40名が参 加しま した。また、東京都内観光ツアーも同時に行い、約20名が参加しました。
ICFM5の成果
ICFM5では、コミュニティ、国、地域がそれぞれのレベルで直面している洪水管理上の重要課題について、3日間に渡り、集中的な議論が行われました。ICFM5宣言案は、それを踏まえて、ICFM5議長および特別委員会が作成しました。宣言案はICFM5のホームページでご覧いただけます。
ICFM5宣言案は以下の項目を考慮して作成された。
- 2011年3月11日に発生した東日本大地震および津波のような想定外の事象が現実に起こり得る。
- 社会経済システムがより複雑化し、社会経済活動を構成する要素は相互依存の度合を一層高め、ごく一部の地域で発生した災害の影響でも、マーケットネットワーク(サプライチェーンなど)を通して、短期間に国内外に広がり、地球規模へと拡大し得る。
- 洪水は世界の至る所で頻発し、一度発生すればいかなる国も非常に深刻な社会経済的影響を被るという点で、他の自然災害の比ではない。
- 気候変動は、洪水リスク増大を引き起こす要因のひとつであり、十分注意する必要がある。2009年台湾、2011年日本でそれぞれ発生した集中豪雨の例からもわかるように、豪雨の頻度、強度はともに明らかに増大している。
ICFM5宣言はまた、以下の項目についても宣言する。
- 洪水:リスクから好機へ
- 不確かさが大きい状況での洪水災害管理
- IWRMの一環としての洪水管理
- 社会資本を構成する構造物と非構造物のバランス
- 想定外の災害に対する準備
- 想定外の極端事象およびカスケード効果の評価法
- 予測の科学的進展
- 氾濫原の保護
ICFM5宣言では、以下の項目について同意した。
- HLEP/UNSGABアクションプランの実行。UNSGAB/HLEP(水と災害に関する有識者会合)のアクションプランは、UNSGAB/HLEPが実行に関与している点に特色がある。ICFM5に参加した各国組織、国際組織は、早期警戒システム、災害防止指標、気候変動対策、メガデルタ保全などを含む、会期中議論された重要事項の実行に強い意思をもって取り組まなければならない。
- ICFM5宣言の共有。ICFM5参加者は、承認された宣言を主要国際会議他で共有するべく努めることに同意した。主な国際会議の例は以下の通り。第1回統合的災害リスク研究に関する国際会議(Beijing, 2011)、第6回世界水フォーラム(Marseille, 2012)、リオ+20(Rio de Janeiro, 2012)、第3回災害緩和国際会議(Japan, 2015)など。
- 知識と経験の共有。コミュニティ、国、地域、世界など各レベルでの情報共有は、洪水リスク管理において不可欠である。
研修と教育。ICFM5参加者は、統合的洪水管理の実施には、研修と教育の推進が欠かせないことに同意した。

今後の出版物の予定
- ICFM5宣言の最終版
- プレゼンテーションに使用されたパワーポイント資料(PDFまたは PPS形式)。講演者から許可を得られなかったものは除く。
- 今回提出された論文120件から選ばれた論文の出版。2012年半ばまでにJournal of Flood Risk Managementまたは IAHS Red Book Seriesに掲載予定。現在、出版候補論文の第一回査読をICFM5国際技術委員会に依頼し、論文を送付している段階。第一回査読を通過し、第二回査読へと進む論文の執筆者には、2011年終わりから2012年初めまでに、その旨を連絡(第二回査読には60件の論文を予定)。第一回査読通過がかなわなかった場合、論文は執筆者に返却。
謝 意
今回、ICFM5開催にあたりまして、参加者皆様から様々な形でご支援、ご協力をいただき、会議を成功裡のうちに終わらせることができました。また、WMO、UNESCO、河川整備基金から助成を受けました。併せて感謝いたします。ICFM5が参加者皆様にとっても実り多いものであったことを願っております。また何かお気付きの点ありましたら、ICHARM ICFM5事務局まで遠慮無くお寄せください。
