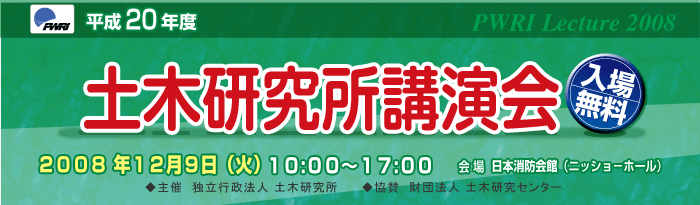| 「韓国の河川再生技術の傾向と課題」 |
韓国建設技術研究院 責任研究員 李 参熙(イー・サンミ)氏 |
<プロフィール> <役職> |
|
<講演概要> |
| 11:05~11:45 |
| 「自然環境を保全するダム技術の開発」 |
| つくば中央研究所 水工研究グループ長 安部 友則 |
| 最近のダム事業では、自然環境と調和のとれたダムの整備と健全な流砂系の実現が求められている。そのため、自然環境の保全を追究した新しい構造型式のダムの設計技術、ダム建設による地形改変を少なくする技術、ダム貯水池堆砂を抑制し下流河川に土砂を供給する土砂制御技術等が研究されている。そこで本講演では、土木研究所がそのために取り組んでいる、川が連続するダム設計、台形CSGダム設計、規格外骨材の評価、岩盤弱層の強度評価、貯水池および下流河川における土砂制御技術に関する最近の研究状況を紹介する。 |
| 13:00~13:40 |
| 「道路交通の地域特有の課題に 対応した研究開発について」 |
| ~正面衝突、冬期路面および郊外部道路の課題を事例に~ |
寒地土木研究所 技術開発調整監 浅野 基樹 |
| 寒地土木研究所では、これまで北海道をフィールドとして主に地域特有課題解決のための研究開発を実施してきた。本講演では、道路関連の研究成果の中から、正面衝突対策としてのランブルストリップスの研究開発、スパイクタイヤ規制後の課題に対応した冬期路面管理に関する研究、広域交通需要をになう郊外部2車線の一般国道の課題に対応した研究について述べる。特にランブルストリップスは北海道以外の地域の共通課題に対する技術として紹介する。 |
| 13:40~14:20 |
| 「衛星雨量情報を活用した 洪水予測システムの開発と普及」 |
| 水災害・リスクマネジメント 国際センター 水災害研究グループ長 寺川 陽 |
| 地上水文情報や地理情報が十分に得られない発展途上国流域における洪水予警報システムの整備に資するため、人工衛星雨量情報の活用を念頭においた洪水予測システムを民間との共同研究によって開発した。本システムは、インターネットを通じて自由に入手可能な地形・土地利用データによって、モデルの構築及びパラメータの設定を自動的に行える点に最大の特徴がある。ICHARMは本システムを用いて、発展途上国の技術者と一緒に洪水予警報の実現に取り組むプロジェクトに着手した。本講演では、システムの概要及び普及方策について述べる。 |
| 14:20~15:00 |
| 「構造物メンテナンス研究センターの設立とその活動」 |
| 構造物メンテナンス研究センター 橋梁構造研究グループ長 吉岡 淳 |
| 高度経済成長期に大量に建設された我が国の社会資本が今後一斉に高齢化を迎える中、構造物の健全性を評価し、適切に維持管理を行っていく技術の確立が急務である。このような背景のもと、土木研究所では、本年4月、既存の組織を再編し「構造物メンテナンス研究センター」を設立したところである。センターは、構造物保全技術の中核的な研究拠点として、①現場の支援、②研究開発、③情報交流の場を主要な役割と捉え、活動を行ってきている。本講演では、センター設立の背景と組織の概要、活動の方向性について紹介する。 |
| 15:15~15:35 |
| 「土木研究所の成果の普及と社会的効果」 |
| つくば中央研究所 技術推進本部長 福田 正晴 |
| 「使われてこそ新技術」-土木研究所は、この視点の下、新技術の開発、活用・普及に取組んでいる。本講演では、新技術の開発動向と、知的財産権の取得・活用、新技術の普及活動など成果普及の概要と展望を述べ、さらに土木研究所が推奨する新技術の事例を挙げ、成果普及の実際を紹介する。また、毎年度公表している研究成果の経済効果など社会的効果について述べる。 |
| 15:35~15:55 |
| 「岩手・宮城内陸地震被害の概況」 |
| 構造物メンテナンス研究センター・耐震総括研究監 松尾 修 |
| 今年も6月に岩手・宮城内陸地震が発生し多大な被害が生じた。この地震による特徴的な被害の数例を紹介し、併せて関連する土研の取り組み状況などを紹介する。 |
| 「必ず来る大地震」 |
| 防災情報機構NPO法人会長 伊藤 和明氏 |
<プロフィール> <主な著書> |
| <講演概要> 日本列島の周辺では、4枚のプレートがひしめきあっているため、プレートの境界部や内陸の活断層などに歪みが蓄積し、それが解放されるときに地震が発生する。海溝型の大地震としては、東海地震や宮城県沖地震が切迫しているとされており、内陸の活断層の主なものについても、将来の地震発生に関する確率評価がなされている。また、首都圏直下地震の切迫性も指摘されているところである。 ここ数年の地震発生の状況をみると、これまで殆ど注目されていなかった地域で、規模の大きな地震が起き、思いがけない災害を招いている。まさに、地震はいつどこで起きるかわからないことを物語っているといえよう。 岩手・宮城内陸地震では、大規模な土砂災害が多数発生したし、能登半島地震や新潟県中越沖地震では、老朽化した木造家屋の倒壊が目立った。1995年の阪神・淡路大震災では、死者の約8割は家屋の倒壊によるものであった。そのため中央防災会議では、建築物の耐震化が、今後の地震防災対策における最重要課題と位置づけている。 日本列島では、1948年福井地震から1995年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)まで、地震動だけで100人をこえる死者をだした地震は発生していない。この静穏の間に、都市は立体的に過密となり、さまざまな危険物を蓄積してきた。その時代に造られた建物やまちづくりそのものが、いかに脆弱だったかを露呈したのが、阪神・淡路大震災だったといえよう。 必ず来る大地震に備えて、市民の防災意識を高め、ハード・ソフト両面での環境整備を行うことが、いま求められている。 |