|
実験河川には、瀬や淵や河岸植物がある多様な区間と、河道を直線にし、川幅を広げた単調な区間があります。それぞれ、中小河川の昔の姿と、改修後の姿をモデルにしています。建設省では平成2年より、「多自然型川づくり」が始まりましたが、それ以前に改修され、そのまま放置されている河川も少なくありません。ここでは、2つの区間における魚類の生息状況を比較し、今後の復元のあり方について考えてみましょう。
|
 |
A.未改修区間をイメージ
(瀬や淵のあるハビタット研究ゾーン) |
B.従来型の改修区間をイメージ
(平坦で単調な自然河岸形成ゾーン) |
|
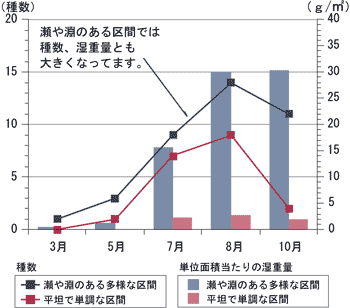
●調査はどうやったの?
魚類調査は電気ショッカーを用いています。
相対的な比較ができるように、単位面積当たりの採捕時間を同じにしています。
●グラフの「湿重量」って?
採捕した魚類全ての合計体重を採捕区間の面積で割ったものです。
|
|
| ■ 瀬と淵がある多様な区間と平坦で単調な区間における採捕種数、湿重量の違い |
 |
|
|
多様な区間では単調な区間と比べて、魚類の生息状況が大きく異なることが解ります。今後は、このような環境が悪化した河川の復元が必要となります。センターでは効果的な復元方法についても研究を行っています。
担当:萱場 祐一
|
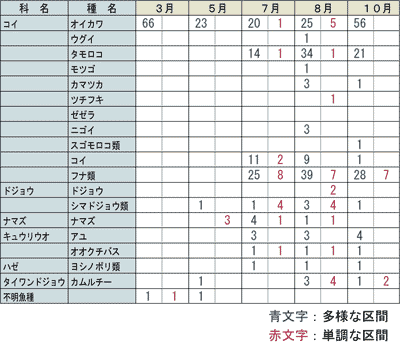 |
■ 各月の採捕魚種
生息魚類の季節変化
多様な区間では、春〜夏にかけて、優占種に変化が見られました。
特に、フナ類やタモロコ類が多くなっています。また、この2種とナマズ、シマドジョウ等は実験河川で産卵が確認できました。 |
 |
|
|