|
平成2年から「多自然型川づくり」が始まり、生態系に配慮した川づくりが行われるようになりましたが、それ以前に改修工事が行われ、単調な環境となっている中小河川も少なくありません。
今後は、こうした河川の環境を復元することも必要になると考えられます。ここでは、単調な環境の区間に様々な復元工法を実施した場合に、魚類の生息状況がどのように変化したかを比較してみましょう。
復元工法を実施した区間は河道が直線で川幅が他の標準的な区間よりも広くなっていました(標準的な区間は川幅がおよそ3mに対し、復元工法実施区間はおよそ6m)。また、河床が平坦なため、瀬や淵の見られない単調な区間でした。
復元工法は、ディフレクターという水制工を河岸から突き出し、平水時のみお筋を蛇行させるとともに、所々に淵を人為的に形成し、ここにベーン工等の構造物を設置することにより淵における土砂の埋没を防止しています。更に、早瀬工を設置することにより、河道内に瀬−淵構造を再現しました。また、河岸沿いの土砂堆積促進と河岸植生の早期回復を目的として、木杭やマウンドを河岸沿いに設置しました。
復元工法を実施した区間では魚の個体数・種類数ともに実施前よりも増えていることがわかります。復元工法により水深・流速が多様な環境が創出されたためだと考えられます。
これらの復元工法は施工した時点で完成するのではなく、浸食・堆積といった河川の自然作用により、最終的に右のイラストのような姿になることを目標としています。
センターでは今後も継続的に調査を行い、復元工法の効果を検証する予定です。
担当 : 萱場 祐一・島谷 幸宏・田中伸治
|
 |
| 復元工法実施前の写真 |
復元工法実施後の写真 |
|
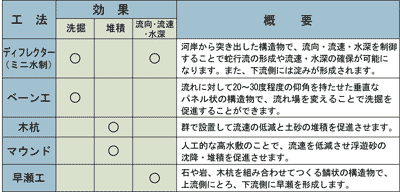 |
| ■ 実験河川で用いられている復元工法 |
 |
|
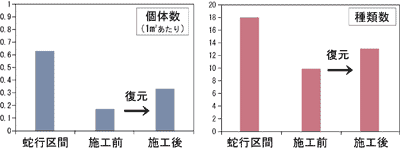 |
| ■ 復元工法による魚類の生息状況の回復程度(8月の調査結果より) |
 |
|
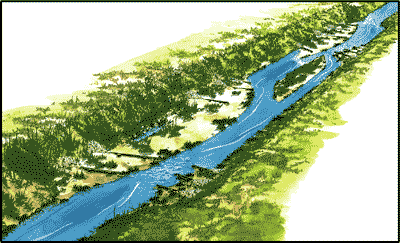 |
| ■ 将来予想イラスト |
|
|