|
流域に降った雨は、さまざまな箇所で貯留されながら河川へ到達し、河道内でも同様に貯留され流下していきます。この効果を治水に利用するものとして流出抑制対策があり、河道外においては遊水池等が整備されることがあります。これは「流域内に降った雨を一時的に貯留することにより下流への流水の到達を遅れさせ流水の集中による氾濫を防ぐ」治水対策の一手法です。
今回は河道内の治水と環境という観点から、動植物にとって重要なハビタットであるワンドや河原(ポケット部)の流出抑制について着目し、河道内でのその状況と活用の可能性について調べました。
実験河川で出水実験を行い水位・流量の計測結果から、貯留の状況を本川部、ポケット部、浸透分について把握しました。それぞれの貯留量は、全体の貯留量に対して本川部が約60%、ポケット部が約10%、浸透分が約30%でした。
浸透による貯留量が予想以上に大きく、また洪水初期に貯留量が増大していることが確認されました。これは初期の流出の著しい出水ほど、下流への流量の低減が大きいことを示しており、流出の早い都市河川等では、これらの貯留を治水対策として利用する可能性も考えられます。
今後、浸透による貯留について地下水位等の計測により、さらに定量的に把握するとともに、植生の状況による貯留についても調査する予定です。
担当 : 白江 健造・戸谷 三知郎
|
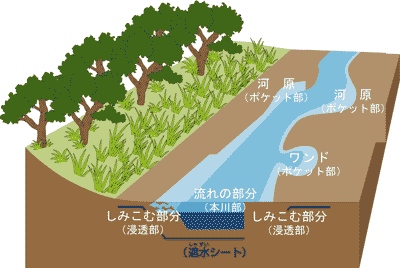 |
| ■ 実験河川イメージ |
|
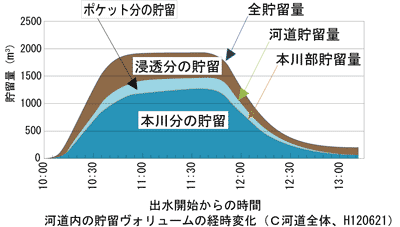 |
| ■ 全貯留量の内訳 |
 |
|
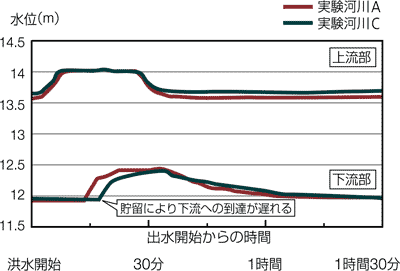 |
| ■ 貯留変化量の経時変化 |
 |
|
|