|
礫質の河原は、カワラヨモギ、カワラハハコ、カワラサイコなどの河原固有の植物からなる特徴的な生態系が発達する場所です。
しかし最近では人間活動に伴って外国から持ち込まれた外来植物が生育場所や資源を奪ってしまうことにより、在来の植物が衰退してきているといわれています。
ここでは、外来植物の選択的な除去が在来植物の生育にもたらす効果を調べました。
河原植物保全研究ゾーンに20の方形調査区を設け、2000年3月に河原に生育する在来植物(カワラサイコ、カワラヨモギ、カワラナデシコ、カワラマツバ、カワラハハコ)の種子を播種しました。
調査区のうち10個では月に一度、調査区内の外来植物をすべて抜き取りました(除去区)。残りの10個の調査区では除草を行わず対照区としました。
調査区内ではオオキンケイギク、オオフタバムグラをはじめ21種の外来植物が発生し、対照区では外来のオオフタバムグラが優占する単調な植生になりました(図-1)。
播種した植物のうち、2000年10月の時点ではカワラヨモギ、カワラサイコ、カワラマツバ、カワラナデシコの4種が確認されました。これらの植物は、除去区においてより多く発生していました(図-2)。
カワラヨモギは、除去区でより大きく成長し、より高い頻度で開花していました(図-3)。
外来植物の繁茂により、植物の発生種数・個体数・成長が抑制されることが示されました。
外来植物が優占すると、見た目にも単調な景観になりました。本来の河原らしい景観・生態系を維持するためには、外来植物の侵入を防止するとともに、既に侵入してしまった外来植物を除去するための管理が必要と考えられます。
担当 : 西廣 淳・皆川 朋子
|
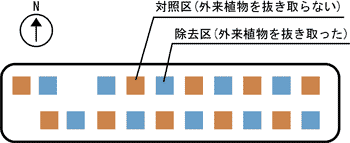 |
| ■ 河原植物保全研究ゾーンにおける調査区の設置 |
|
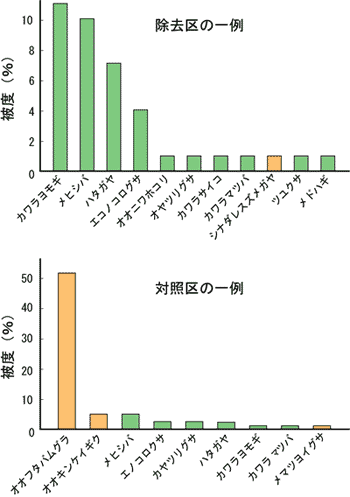 |
| ■図-1 調査区内に発生した植物種毎の被度(橙色は外来植物) |
 |
|
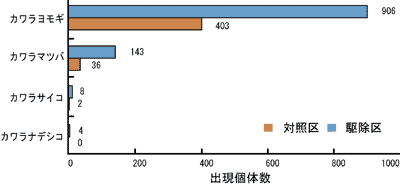 |
■図-2 河原植物の出現個体数
(各処理の全調査区合計=40m2あたり) |
 |
|
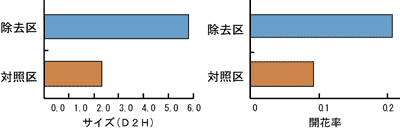 |
| ■図-3 カワラヨモギのサイズ(左)と開花率(右) |
 |
|
|