|
�@�^�����̐��̗���́A���ɖ��C�͂��y�ڂ��ĉ͏��ޗ������A�����̐����ɉe�����y�ڂ����Ƃ��m���Ă��܂��B
�@��ʂɁA�^�����̗��ʂ����������[���傫���Ȃ�Ɛ��̖��C�͂��������܂��B�������A�앝�������������͐�ł͉݂͊ɐA�����ɖ���Ƃ�����ƈ�������ۂ��N����܂��B�A������R�ƂȂ蓯�ꗬ�ʂł��A�����̒ቺ�A���̖��C�͂̒ቺ�������i�ʐ^-1�E�}-1�j�A�͏��ޗ��������ɓ����Ȃ��Ȃ�̂ł��B
�@�����ł́A�݂͊̐A����������������i�V���j�ƐA��������������i�X���j�ɂ����門�C�́i�����ł́A���C���x��2��Ƃ����w�W���g���܂����j�Ɖ͏��ޗ��̈ړ���ԂƂ̊W�𐄒肵�Ă݂܂��傤�B�͏��ޗ��̈ړ���Ԃ��u�T�F�ړ����Ȃ��v�A�u�U�F����]����Ȃ���ړ�����v�A�u�V�F��ꂩ�畂�サ�Ă܂����~����v�A�����āA�u�W�F���サ���܂܈ړ�����v�A�̂S�ɕ��ނ��܂��B�A�����Ȃ��ꍇ�ɔ�ׁA�A���̂���ꍇ�́A�͏��ɓ������C���x���傫���ቺ���A�͏��ޗ��̈ړ���Ԃ��傫���ω����邱�Ƃ�����܂��B�Ⴆ�A�����͐�ɂ悭������1�����̗��a�̍��́A�^�����i�Qm3/���j�A�����Ȃ��ꍇ�́A�V�̏�ԁi����ƒ��~���J��Ԃ��ĉ����Ɉړ�����j�ł����A�A��������ƇU�̏�ԁi����]����Ȃ���ړ�����j�ւƕω����܂��B�܂��A10mm���I�̏ꍇ�́A�U�i����]����j����T�i�ړ����Ȃ��j�ƂȂ邱�Ƃ��킩��܂��B�i���a���Œ肵�āA���C���x���ቺ�����Ƃ��ɐ}���̐����邩�A�����Ȃ������ړ���Ԃ̕ω���m��ڈ��ł��j
�@���̂悤�ɁA�앝�̏������͐�ɂ�����݂͊̐A���́A�͏��ޗ��̈ړ���ʂ��Đ�̐��Ԍn�ɐ[���ւ���Ă���ƍl�����܂��B�앝�A���[�A���C���x�A�͏��ޗ��̗��a���H�w�Ŏg�p�����ړx����̐��Ԍn�̗�����������ꍇ������܂��B
�S�� �F ���� �O
|
 |
|
���ʐ^-1�@�݂͊ɔɖ���A���̏� |
|
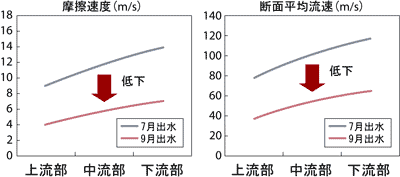 |
���}-1�@�����͐��2m3/s�𗬉����������́u���C���x�ƒf�ʕ��ϗ����v
�����͐�ł́A�݂͊̐A����������������i�V���j�ƐA���̐���������i9���j�ɁA�^���������̐����ʂ𑪒肵�܂����B�}�P�͗���2m3/s�𗬂����Ƃ��́A�����A���C�́i�����ł́A���C���x�Ƃ����w�W���g���܂����j�������܂��B�A��������ƁA�����A���C���x�Ƃ��ቺ���邱�Ƃ�������܂��B |
 |
|
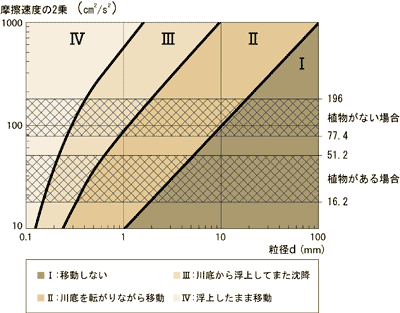 |
���}-2�@�A���̔ɖɂ��͏��ޗ��̈ړ��`�Ԃ̕ω�
�オ�A���̂Ȃ��ꍇ�i�V���j�A�����A���̂���ꍇ�i�X���j�̖��C�́i���C���x�̂Q��j�̒l�������܂��B�����͐�͌��z��앝���ω����邽�߂��̒l�ɕ�������܂����A�S�̓I�ɐA���̂Ȃ��ꍇ�̖��C�͂��傫���A�͏��ޗ��̈ړ��`�Ԃ��قȂ�܂��B |
 |
|
|