外来植物は河川の生物多様性を脅かす主要な要因の一つです。そのため、外来植物の駆除や適切な管理は、河川の生態系保全における重要事項となっています。
植物の多くは、地上に見えている個体よりもはるかに多数の種子を土壌中に蓄積しています。このような土壌中の種子の集団のことを「土壌シードバンク」といいます。土壌シードバンク中に外来植物の種子がたくさん存在するのであれば、その発芽の抑制や、発芽した個体が種子をつける前に抜き取るという管理を継続することが必要になります。
では、河川の土壌中にはどのような植物の種子が、どのくらい含まれているのでしょうか?
自然共生研究センターの「蛇行ゾーン(上流)」「直線河道部(ワンドゾーンに隣接する河道部)」「ワンドゾーン」のそれぞれで砂礫の採取を行い、「実生発生法」により土壌シードバンクを調査しました。(写真a〜e)
調査では、56種3,013個体の実生が確認され、そのうち外来種は15種2,148個体を占めていました(図-1)。ワンドゾーンでのヒレタゴボウのように、地上植生で優占度が高く土壌中の種子量も多い例が認められた一方、メリケンガヤツリ、アレチハナガサなど地上植生ではそれほど優占していなかった外来種でも、土壌中に多くの種子を蓄積しているものがあることが示されました。(図-2)
土壌シードバンクに含まれる種は、環境の変化などに応じて発芽し、場合によっては優占する可能性があります。本来の河原らしい植生を復元し、長期的に維持するためには、目に見える地上植生だけでなく、土壌シードバンクという「地下の植生」も考慮した管理が必要だと考えられます。
自然共生研究センターでは、今後も、外来植物の侵入の実態や、有効な駆除・管理方法についての研究を進める予定です。
担当:西廣 淳・皆川 朋子
|
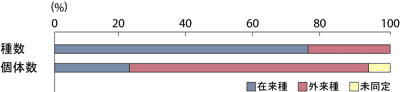 |
■図-1 土壌シードバンク調査で検出された「在来・
外来種の種数」と「個体数」
実験河川B,Cの「蛇行ゾーン(上流)」「ワンドゾーン」「ワンド付近の直線部」から30cm×30cm×深さ5cmの砂礫を1標本とし、各河川の各ゾーンから2標本ずつ採集して調べた。それらの全てを含めたデータを示す。 |
 |
|
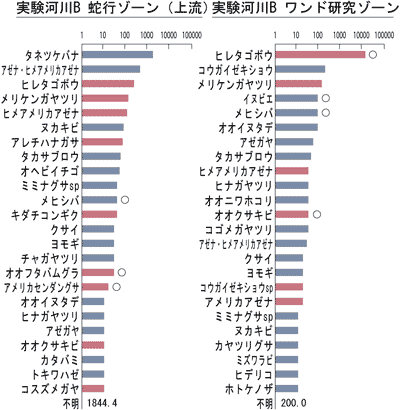 |
■図-2 土壌シードバンク調査で出現した実生数
実験河川Bの「蛇行ゾーン(上流)」「ワンドゾーン」で採取した砂礫から検出された実生数について、1m2上あたりの数に換算した値を示す。軸は対数である。種は合計数が多い順に並べた。また、地上植生において最も優占度が高かったものに○をつけた。赤色のバーは外来種であることを示す。 |
 |
|
|