洪水時の川は、水の濁りだけでなく流木等様々な物質が流れていることを確認できます。では、平常時と比べて流れている物質にどのような違いがあるのでしょうか。実験河川では平常時(0.1m3/s)と出水時(2m3/s)に流下する物質量を測定し、両時期における流下物質の特徴を調べました。
断面通過物質量の測定は、実験河川Bの上流端と下流端で行いました。平常時実験は2002年7月12日〜13日(1回目)、7月27日〜28日(2回目)に行い21時から翌日の21時までの24時間観測、出水時実験は2002年7月31日の10時〜13時までの3時間観測を行いました(図-1は上流端と下流端の時間−流量曲線)。
一般に、断面通過物質量の測定は、ある断面における流量の観測と水質調査を同時に実施し、水中に含まれている物質濃度に流量を掛けることにより断面通過物質量を算出します。しかし、この方法では、1mm以下の物質のみが対象となるため、沈水植物片等の大きな物質が分析対象となりません。そこで、上流端及び下流端で水質調査と同時に、ネットによる1mm以上の物質の採取も実施し、正確な断面通過物質量の把遍を試みました。
ある時刻での上流端及び下流端での通過量の差を、河道内への蓄積・河道内からの流出と考えて、平常時は24時間の合計、出水時は3時間の合計値として有機態炭素について整理して示しました(図-2)。平常時は、1mm以下の物質に含まれる有機態炭素通過量が上流端、下流端とも大きく、河道内に蓄積される量(もしくは河道内から流出する量)は非常に小さいことが解ります。また、1mm以上の物質は1mm以下の物質と比較すると通過量自体が非常に小さく、平常時の物質輸送の担い手として粒径の小さい物質(懸濁態と容存態の双方)が重要であることが理解できます。一方、出水時は、1mm以上、1mm以下とも下流端における通過量が大きくなり、河道内からの流出が大きくなっていることが解ります。特に1mm以上の物質は河道内部から大量に流出しており、出水時の物質輸送に重要な役割を果たしています。
実験河川は流域や高水敷からの流入負荷がなく、河道内から流出する物質量を正確に把握することが可能です。今回の出水実験は3時間という短いものでしたが、河道内からの物質流出量は平常時24時間における河道とのやりとりの量と比較しても非常に大きなものであることが解ります。物質輸送における出水の意義は大きいのです。
担当:萱場 祐一
|
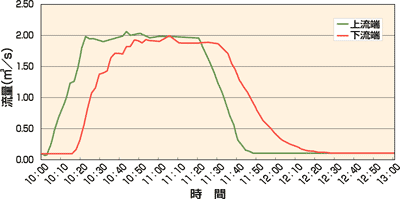 |
■図-1 出水時の時間−流量曲線
上流端と下流端における時間流量曲線を示す。観測は13時まで実施しているが、流量は下流端においてでも12時30分頃には平常時の流量0.1m3/sまで低下している。 |
 |
|
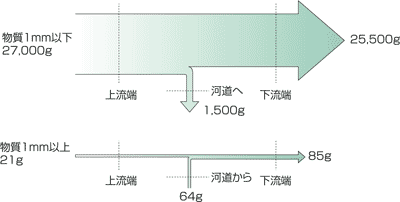 |
平常時の物質収支(有機態炭素)
7月12日〜13日 21:00〜翌21:00(24時間)
|
|
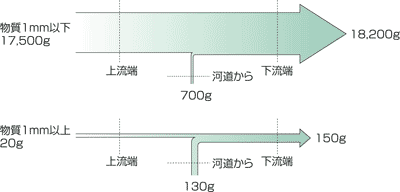 |
平常時の物質収支(有機態炭素)
7月27日〜28日 21:00〜翌21:00(24時間) |
|
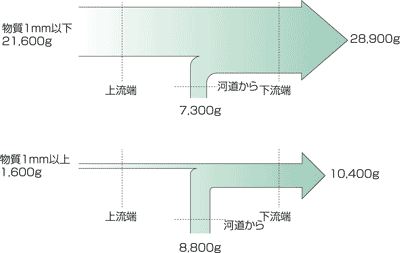 |
| 出水時の物質収支(有機態炭素)7月31日 10:00〜13:00(3時間) |
|
■図-2 平常時及び出水時の物質収支状況(有機態炭素)
上から、平常時1回目、平常時2回目、出水時を示す。平常時における物質1mm以上については、量が少ないため太さを拡大してある。 |
 |
|
|