|
● 研究目的
自然植生からコンクリート護岸に変わった際に失った機能を把握することは、コンクリート護岸河川において、生物の生息環境改善を考える場合非常に重要になります。
植生護岸の機能を、植物のカバー効果(陸上部・水中部)に注目し、それぞれの植物カバーがもつ機能を検証する実験を図-1のように各処理区を設定して行いました。
● 調査方法
実験は自然共生研究センター内にある実験河川Aで、9月中旬に各処理区の設定を行い、10月中旬にエレクトリックショッカーによる魚類そして甲殻類の生息量調査を行いました。
● 法面タイプによる魚類の生息量比較
魚類の分布にとって、陸上カバーより水中カバーの方が重要でした。また、コンクリート護岸の魚類生息量が最も小さくなりました。(図-2)
● 法面タイプによる甲殻類の生息量比較
甲殻類の分布には、水中カバーの存在が非常に重要でした。また、コンクリート護岸では甲殻類はほとんど生息していませんでした。(図-3)
● 考察
水際にある水中カバーの存在が、水生生物の分布に強く影響を与えることが実験によって示されました。
水際に植物があると水際の流速が低減し、横断面の流速分布が複雑になります。さらに水生生物にとっての避難場である水中カバーを提供します。このような環境が水生生物にとって好ましいと考えられました。
● 今後の課題
今後はコンクリート護岸河川を対象に、どのような水中カバーが生物の生息環境改善に効果があるのか、実験的に検証することを検討しています。
担当:河口 洋一・水野 徹
|
 |
|
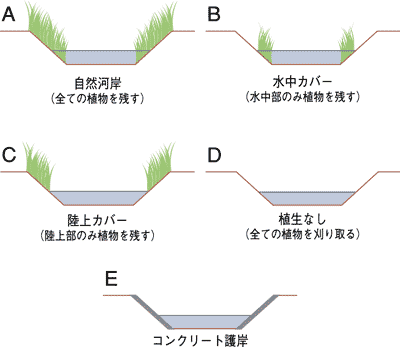 |
| ■図-1 処理区の設定 |
|
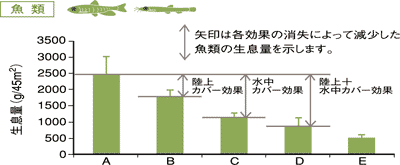 |
■図-2 水際域の構造と魚類の生息量比較
|
 |
|
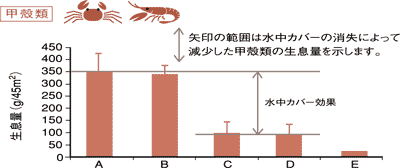 |
| ■図-3 水際域の構造と甲殻類の生息量比較 |
 |
|
|