|
● 研究の背景と目的
付着藻類は河川における有機物の供給源、すなわち一次生産者としての役割を担っていて、河川に生息する底生動物やアユ等の魚に餌を供給します。付着藻類がどの程度の有機物を生産するのか、という問いは、生態系が依存しているエネルギーの由来を知る上で非常に重要であり、河川の自然環境の保全や再生事業を行う上で今後必要な情報となっていくでしょう。今まで河川における生産速度の測定は技術的に難しかったため、この実態はあまり明らかになっていませんでした。このため、平成15年度は、河川において生産速度を簡易に推定する方法を開発し、これを実験河川に適用して生産・呼吸速度の実態を明らかにしました。
● 生産速度の推定方法と実験方法
生産速度は2地点間の溶存酸素濃度差から推定しました。2地点間の溶存酸素濃度差は、夜間は大気からの再曝気と水中の生物群集による呼吸により、昼間はこれに光合成による酸素供給が加わり、決まります。夜間光合成の影響がない時間帯において2地点において溶存酸素濃度を測定し、ここから単位時間当たりの再曝気量と呼吸量を推定し、この推定値から昼間の光合成速度を算出するというのが推定の原理です。実験は2003年6月4日〜10日に実験河川BとCを用いて行いました。両実験河川とも流量を0.1m3/sとし、両実験河川の上流区間、中流区間、下流区間の上流・下流地点それぞれ合計8箇所に連続観測できる溶存酸素濃度計を設置しました(図1)。
● 結果と考察
実験河川Bの上流区間で測定した溶存酸素濃度の日周変化を代表例として示します(図2)。上流地点と中上流地点の溶存酸素濃度を比較すると、光合成によって酸素が供給される早朝から夕方までは中上流地点が、光合成の影響がなくなる夕方から翌日早朝までは上流地点で、それぞれ溶存酸素濃度が高くなりました。この結果を基に各測定日(零時〜翌日零時)における日総生産速度と日呼吸速度を推定し、6月4日から9日までの平均値を算出しました(図3)。上流区間と下流区間では相対的に日総生産速度・日呼吸速度とも大きく、中流区間で小さくなりました。中流区間は河床勾配が緩やかなため水深が相対的に大きく、河床まで到達する日射量が減少すること、また、中流区間は河床材料に砂分が多く付着藻類を始めとした生物群集の生息量が減少すること等が理由として考えられますが、原因の特定は今後の課題として残されました。今回適用した手法は比較的汎用性が高く、実際の河川でも適用が可能です。生態系におけるエネルギーの流れを知る上で今後有効なツールとなりそうです。
担当:萱場 祐一 |
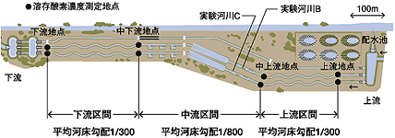 |
| ■図-1 溶存酸素濃度測定位置 |
 |
|
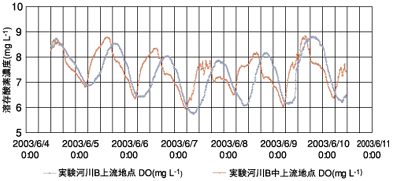 |
■図-2 実験河川の上流、上中流地点における溶存酸素濃度の日周変化
|
 |
|
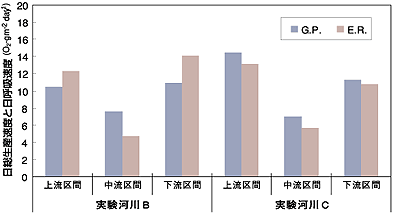 |
| ■図-3 実験河川B及びCの日総生産速度(G.P.)と日呼吸速度(E.R.)の平均値 |
 |
|
|