|
川の魚のすみかとして、水際の植物や深みなどが大切だといわれていますが、そういった報告の多くは、成魚(大人)や未成魚(ほぼ大人)についてのものです。では、仔魚(新生児)や稚魚(幼児)は、どんな場所に棲むのでしょうか。これを明らかにするために、実験河川では、オイカワ、タモロコといった本河川で産卵しているコイ科魚類を対象として、通常流している流量時(基底流量時)と人工的に増量して流した流量時(増水時)(写真1)に水深や流速等の物理環境調査と稚仔魚の捕獲調査を行いました。
その結果、稚仔魚は基底流量時には流れの遅いワンドと水際部のみで確認され、流れの速い流心部では確認されませんでした(図1)。一方、増水時にはワンドに生息が限定されただけではなく、仔魚の個体数が増水に伴い増加していきました(図2)。この理由としては、増水時には、流心部や水際部の流れが早くなるに対して、ワンド部はならないこと(図3)が関係しています。すなわち、水際部の流れが早くなり定位できなくなった仔魚が流れの遅いワンド内に流入してきたことが考えられました。従って、増水時でも流れが遅く保たれるくぼみは、稚仔魚の恒常的な生息場所として重要であるといえます。
しかし、こういったくぼみは、河岸の地形をまっすぐにする改修工事により失われ易い環境です。成魚や未成魚が棲み産卵できる環境も重要ですが、魚類が生活史をまっとうするためには、生まれた子供らの保育器やゆりかごとしての環境にも目を配ることが大切です。少子高齢化が問題視されている我々人間社会だけではなく魚社会でも子供達が安心して生育できる川のバリアフリー化を進める必要があります。
担当:佐川 志朗・荒井 浩昭
|
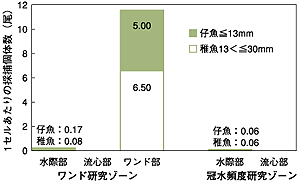 |
■図-1 基底流量時における稚仔魚の確認状況
|
 |
|
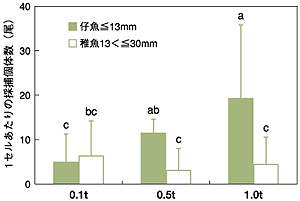 |
■図-2 増水時におけるワンド部での稚仔魚の確認状況
|
 |
|
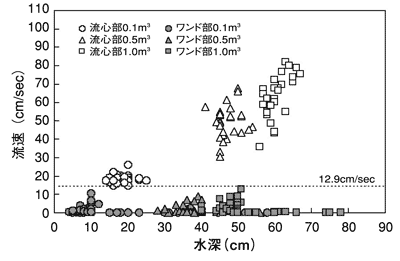 |
■図-3 増水に伴う水深および流速の変化
|
 |
|
|