|
河川の流量を増減させると、それに伴い流速や水深が変化するため、魚類の群集構造にも変化が生じることが考えられます。しかし、これらに関する研究は、流量の変化が予測できない自然の河川では実施することが困難です。良好な河川環境の保全には適正な流量が必要であり、河川の維持流量は、動植物、景観、水質等の必要流量から算定されています。しかし、河川流量と動植物の生息との関係に関する科学的な研究はほとんどみられないことから、維持流量決定の際の基礎資料として、以上に関する知見を収集していくことは大変有意義であるといえます。実験河川では、直線河道部の瀬を用い、河川流量を時間的に変化させ(図1)、それに対する魚類の反応様式を把握する実験を行いました。
その結果、遊泳魚の割合、個体数、サイズに流量の変化に追従した反応がみられ、流量の増加に伴い、大きな遊泳魚が増えるといった現象が認められました(図2、3、4)。一方、底生魚には流量変化との連動は認められず、魚類の遊泳形態によって流量変化による影響が異なってくることが示唆されました。
また、流量変化との連動が認められた遊泳魚の反応様式を魚種別にみてみると、オイカワは顕著に反応しているのに対して、その他の遊泳魚には流量との関連性は認められませんでした(図5)。従って、遊泳魚の中でも種によっては流量変化に敏感に反応する種とそうでない種が存在することが示唆されました。
以上より、ある魚種を保全の対象として維持流量を決定する際には、対象種の反応様式を実験等で把握した上での検討が必要であると考えられます。
担当 : 荒井 浩昭・佐川 志朗 |
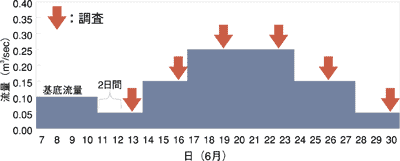 |
| ■図-1 流量調査および調査日 |
 |
|
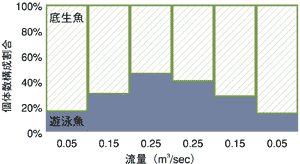 |
■図-2 遊泳魚と底生魚の流量別個体数割合
|
 |
|
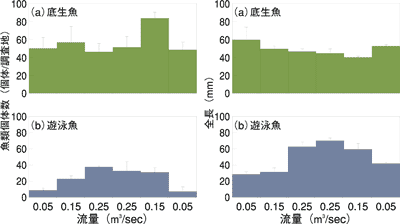 |
| ■図-3 魚類個体数の流量別変化 |
■図-4 魚類個体数の流量別変化 |
 |
|
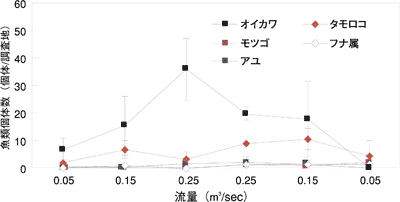 |
| ■図-5 魚類別個体数の流量別変化 |
 |
|
|