|
一般に水際域は河道の直線化や拡幅など人為的な影響を受けやすい領域といえます。
現在広く用いられている環境保全型護岸については、自然状態の水際が持つ機能のどの部分が護岸構造によって創出できるのかを考えていくことが重要です。そのためにはまず、自然状態の河岸形状や、それぞれの河岸を特徴付ける物理環境要素、魚類による利用形態を理解する必要があります。
そこで岐阜県の牧田川において、写真1のようにツルヨシの繁茂する河岸(植生河岸)と水際に凹凸のある河岸(入り組み河岸)およびコンクリート護岸(コンクリート河岸)の3タイプの水際を取り上げ、潜水観察による魚類調査と物理環境調査を行いました。
その結果、魚類の生息量は植生河岸で最も多く確認され、コンクリート河岸ではごく僅かしか確認されませんでした(図1)。また、各水際タイプで確認された魚類の多くは稚魚や仔魚でした(図2)。物理環境としては、植生河岸と入り組み河岸には、流速が0に近い遅い領域があるのに対し(図3)、コンクリート河岸にはそのような領域がなかったことが大きな特徴と言えます。
したがって、流れの緩やかな水際域はとくに遊泳力の弱い稚仔魚にとって重要な空間であり、コンクリート河岸に見られた流れの速い場所は利用しにくい環境だったと考えられます。さらに、植生河岸のように植物が水面を覆い水際周辺の照度を低下させる環境は(図4)、捕食圧を低下させるなど生息環境を改善させていることが考えられます。このようなことから、実際の川づくりにおいても、水中では低流速域をつくる工夫や陸上では水面の照度を低下させる工夫といった、自然の水際に見られる事象を参考にした水際処理が望まれます。
担当:長谷川 浩二・河口 洋一
|
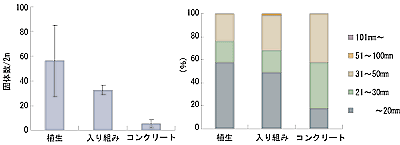 |
| ■図-1 魚類の生息量 |
■図-2 全長構成割合 |
 |
|
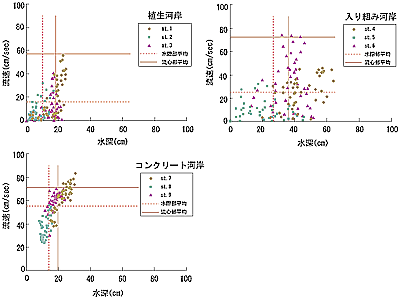 |
■図-3 水深・流速分布
|
 |
|
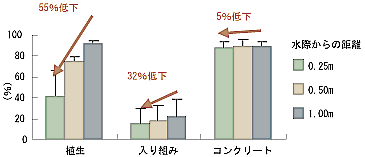 |
■図-4 相対照度
|
 |
|
|