|
● 研究の背景と目的
河川は常に流量を変動させ、時には極端な出水によって生物に大きな影響を与えます。特に水中に生息する魚類は河川の流量変動に大きく影響を受けながら河川内に生息すると考えられます。出水時の魚類行動特性、特に水理特性{流量、流速、加速度(流速の時間変化)、以下、水理特性}との関連を深く理解することは魚類にとって良好な河川環境を保全・復元する上で重要です。このような背景から、自然共生研究センターの実験河川を利用し、出水時の魚類行動と水理特性の関係を把握する研究を行っています。
● 研究の方法 自然共生研究センターの実験河川で、人工出水(流量0.4m3/s〜2m3/s)を複数パターン発生させ実験河川内に魚類(コイ及びギンブナ、以下、供試魚)を離しその行動を追跡しました。魚類行動の追跡は実験河川周辺に生息する供試魚に電波発信機を装着して魚類行動を追跡し魚類が利用した場所を記録しました。
人工出水発生時の水理特性を算定するため、1次元不等流計算を行い魚類が定位した場所の水理特性を算定し、魚類行動との関係性を把握しました。
● 結果と考察 出水時、供試魚は流速と加速度に対応した行動をとりました。
魚類の流速に対する遊泳能力は体長に関係することが知られ体長の2〜3倍程度の流速が移動できる限界といわれます。図−1に示す供試魚の体長は約0.2mのため0.4〜0.6m/sが移動限界であると考えらます。供試魚が上流への移動する間の流速は約0.5〜0.6m/sで供試魚の移動限界の流速と概ね一致しています。このことから、供試魚は移動限界以下の流速になったタイミングで上流へ移動し下流への移動を回避している可能性が高いと考えられます。
では、流速減少のタイミングはどのように把握するのでしょうか?図−2に加速度(流速の時間変化)と魚類移動の関係を示します。供試魚は、加速度が0以下、減少傾向になった時に上流へ移動していることが分かります。加速度の増減は将来的な流速の増減をある程度正確に予測する指標と考えることができます。魚類は、加速度を指標に今後流速が増加するかしないかを評価し上流への移動をタイミングを把握している可能性が高いと考えています。
このことから、魚類は加速度で上流への移動のタイミングを判断しながら、自分の移動限界の流速以下になった時に上流へ移動している可能性が高いと考えられます。
担当:傳田 正利 |
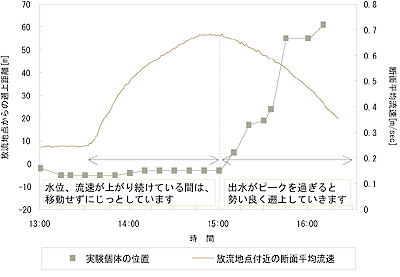 |
| ■図-1 流速-遡上距離 |
 |
|
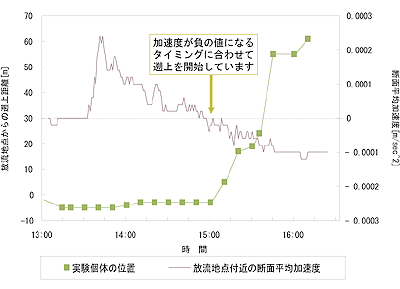 |
■図-2 加速度-遡上距離
|
 |
|
|