|
�� �w�i�ƖړI
�@�䂪���ł͌×����A�l�X�ȕ��@�Ő�ɐ�z�u���邱�Ƃɂ�鎡���s���Ă��܂����B����Őɂ��`�������Ԍ��́A���ނ��͂��߂Ƃ��鐅�������̉B��ꏊ�Ƃ��Ă��@�\���Ă��܂����B�ߔN�ł͂����̋@�\������݁i���j�u���b�N�����{�S���̉͐�H���Ɏg�p����Ă��܂��B�������A�����̐����̉B��ꏊ�Ƃ��Ă̐v��́A�����̉B��ꏊ�̍D�݂������ɂ͔��f����Ă��炸�A�ݒu��̉Ȋw�I�]�����Ȃ���Ă��܂���B�]���āA���u���b�N���̐��ݏꏊ�Ƃ��ċ@�\������ɂ́A�����ɂƂ��Ă̐̌��Ԃ̍D�݂m�ɕ]�����āA��݃u���b�N�J���ɔ��f������K�v������܂��B
�� ���@
�@2005�N12���Ɏ����͐�A�ɋ��I�i�a35�p�j�A���I�i�a20�p�j����ђ��I�i�a4�p�j��3��ނ��I�𐅕ӂɕ~���ς݁A�e�I�ɑ��钲���n��3�ӏ����������܂����B�����Ă��̂܂ܔ��N�ԉ͐�Ɏc�u�����Ă���A2006�N��6�����{�Ɋe�����n�ɂ����ċ��ނ̕ߊl�������s���܂����B�ߊl�́A�e�����n���I�����悤�ɖԂŎd��A���ׂĂ��I����菜������ŃG���N�g���b�N�V���b�J�[��p���čs���܂����B�܂��A��菜�����I�����e����ɐς߂āA�����[�������邱�Ƃɂ��A�e�I�Ō`�����ꂽ�Ԍ��̗e�ς��Z�o���܂����B
�� ���ʂƍl�@
�@�I�𐅕ӂɐݒu���邱�Ƃɂ��A�ǂ��I�T�C�Y�ɂ����Ă�40-50���̊Ԍ����`������邱�Ƃ��킩��܂����i�}1�j�B�܂��A�I1������̊Ԍ��̗e�ς́A���I��8.06R�A���I��1.69R�A���I��0.01R�Ƒ傫���قȂ�܂����i�}2�j�B
�@�e�����n�ŕߊl���ꂽ���ތQ�W�͐}3�̂悤�ɋ敪����܂����B�O���[�vA�͒��I��3�̒����n���܂܂�A�ꐶ���ł���V�}�h�W���E���ƃ��V�m�{��������\��ł����B�܂��A�O���[�vB�́A���I��2�̒����n�Ƌ��I��3�̒����n�i���I��1�̒����n���܂ށj�ɋ敪����A�O�҂̓E�i�M�ƃE�L�S�����A��҂̓^�����R�A���c�S����уt�i������\��ł����B�ȏ���A�I�ɂ��`������鐅���̊Ԍ��͗l�X�ȋ��ނ̐��ƂƂ��ċ@�\���Ă���A�I�̑傫���ɂ�萱�����鋛�ނ̌Q�W�\�����قȂ邱�Ƃ�������܂����B
�@���̂悤�ȈႢ���݂���v���Ƃ��āA�Ԍ��̑傫���A�`�A�����A�Â��A���[�Ȃǂ��e�����Ă���ƍl�����A����19�N�x�ɂ͔��W�I�����Ƃ��āA�ȏ�̈��q���R���g���[�����đz�肵�����ނ�蒅������������s���Ă��܂��i�ʐ^1�j�B
�S���F����@�u�N�E���@���F�E�H��@�~��E��X�@�O�� |
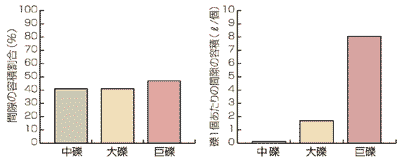 |
| ���}-�P�@�Ԍ��̗e�ϊ��� |
���}-�Q�@�I�P������̊Ԍ��e�� |
 |
|
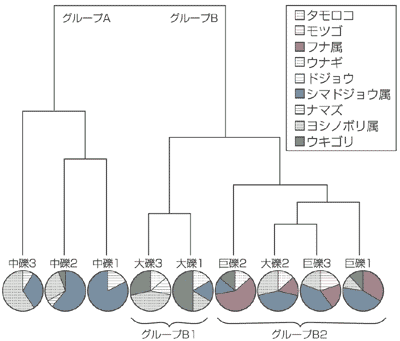 |
| ���}-�R�@�e�I�T�C�Y�ɒ蒅�������ތQ�W�\���̋敪 |
�@�@�@�@ |
|
 |
| ���ʐ^-�P�@�Ԍ������̗l�q |
|