|
● 背景と目的
当センターで過去に行った研究から、河川の水際植生域には流速や照度の低減効果があるため、平常時には魚類の生息に良好な環境になっていることが確認されています。では、増水時にも同様に機能するのでしょうか?その結果について報告します。
● 方法
調査は実験河川Aで行いました。流量は0.2m3/sから0.35m3/s、0.5m3/s、0.8m3/sと2時間毎に変化させました(右上写真)。左岸の草をすべて刈り取り、各流量で水際から1mを「裸地区」としました。右岸の草はそのまま残し、各流量で同様に「植生区」としました。各流量において植生区4地点と裸地区4地点を対象とし、電気ショッカーを用いた魚類調査を実施しました。
● 結果
魚類調査の結果、増水時にも植生区は魚類の巡航速度以下に流速が保たれ、裸地区と比べ魚類の定位場として機能していることと、魚類個体数は0.2m3/s〜0.5m3/sまでは流量が増加すると減少傾向を示しますが、0.8m3/sになると、増加することが明らかとなりました(図1)。
● 考察
0.2m3/s〜0.5m3/sにかけて個体数が減少した理由は、増水による水位変動が起こり、水が濁りはじめ、流速が大きくなることから、魚類はこれを避ける場所を探して上流へ移動したためと考えられます。0.8m3/sで個体数が増加した理由は、流心の流速が突進速度を超え耐えられなくなった魚類は流速が巡航速度以下の植生区に寄ったためと考えられます(表1、図2)。
以上より、増水時には水際植生は魚類の定位場所として機能しているが、流量によって程度が異なることが明らかとなりました。
担当:佐川 志朗・矢崎 博芳・秋野 淳一・大森 徹治 |
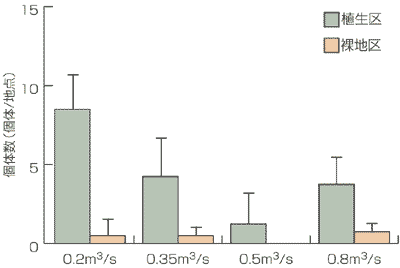 |
| ■図-1 魚類個体数推移 |
 |
|
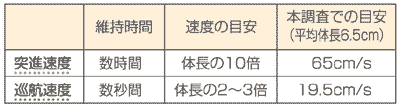 |
| ■表-1 突進速度と巡航速度 |
|
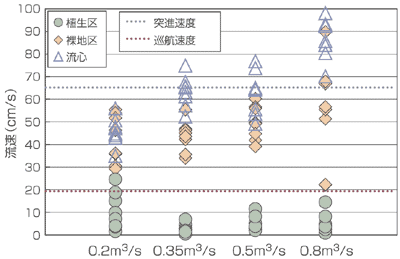 |
| ■図-2 流速推移 |
 |
|