|
● 研究の背景と目的 底生藻が繁茂する河床付着膜は河川に生息する生物の重要な餌資源となりますが、過剰に繁茂しこれが餌として利用されないと、河床に厚く堆積して河床の景観を損ねる、アユの餌資源としての質が低下するといった問題が生じます。流量の改変等により河床環境の変化が予想される場合には、このような問題を事前に予測し、対処することが必要です。本研究では、底生藻の光合成速度を予測し、河床環境の変化を事前に評価する手法の確立を目的とし、底生藻の光合成速度を数理モデルで表現し、これを実験河川に適用してその妥当性を検証しました。
● 数理モデルの概要と実験方法
数理モデルは河床付着膜の内部の基質の動態を拡散方程式で、光合成速度は光量子量、栄養塩濃度を従属変数としたミカエリス・メンテン型の方程式で表現しました。付着膜内部の基質は膜が薄い場合には膜全体で基質の拡散能が高く、膜が厚い場合には膜上部のみで拡散能が高く、膜下部は対象とする基質の分子拡散として与えました(図1)。これは、既往の研究から膜内部の上層は藻類が流れによって躍動し基質供給量が増加するものの(Stoodeley
et al.1998)、膜下部では底生藻と細菌類の集積体(クラスター)が卓越し基質拡散能が低下することが理由となっています(De
Beer et al 1994)。
検証には、2004年9月から2005年7月まで1ヶ月に1度実験河川Cにおいて実測した光合成速度から光飽和条件下における最大光合成速度を算出して用いました。また、計算条件として実験河川の季別の栄養塩濃度、月別の水温を与えました。
● 結果と考察
月別の最大光合成速度の実測値と推定値(単位は1時間、単位クロロフィルaの光合成速度を炭素量で示す)、を示します(図2)。3月と11月以外の推定値は概ね実測値と一致し、冬季に低く、夏季に高い傾向が再現できました。
今後は条件が異なる河川に本手法を適用し、本モデルの検証と改良を行うとともに、摂食量、剥離量をモデルに付加し、流量改変に伴う河床環境の評価手法を確立して行きます。
担当:萱場 祐一
|
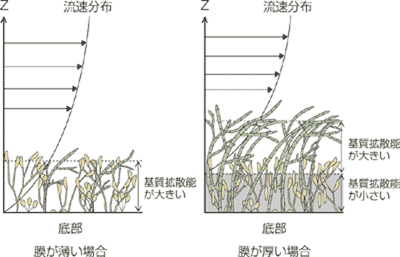 |
■図-1 河床付着膜が薄い場合(左)と厚い場合(右)の基質拡散の
取り扱い。厚い場合には底部への基質の拡散能が低下する。 |
 |
|
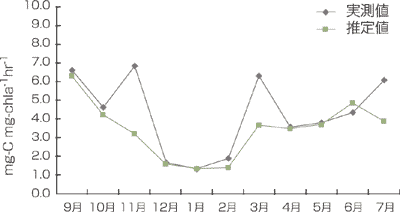 |
■図-2 最大光合成速度の実測値と推定値
最大光合成速度とは光飽和条件下における光合成速度を
示す。
|
 |
|