|
● 背景と目的
河川に堆積する石により形成される隙間(間隙)は魚類の生息場所として機能しています。我が国では、間隙機能を付加した環境保全型の護岸ブロックや根固工(捨石工)等が河川改修に導入されてきました。しかし、魚類の生息を満たすための設計方法は、魚類の間隙の利用特性に関する知見が乏しいため確立されていません。本研究は、石の隙間スケール(隙間一つ一つ)での魚類の利用特性を把握することを目的としました。
● 方法
我が国に優占分布するオイカワ、タモロコおよびフナ属の昼夜における間隙の利用特性について、実験水路を用いて調査を行いました。実験水路は延長25m幅5mの環流式の水路であり、左岸側の側壁が透明アクリル板となっており地下からの水中の目視が可能な構造となっています(左写真参照)。実験に先立ち、水路幅を1.6mに縮小させて左岸側の0.8m幅に大礫および巨礫を層状に敷き詰める改修を行いました。魚類調査は0.1tの流量下(流速0〜0.84m/sec)で連続4日間の日中8時および日没後18時にアクリル面からの目視観察が可能な全355箇所の間隙を対象に実施しました。また、間隙内の物理環境として容積、間隙までの水深、流速、照度の計測を行いました。
● 結果と考察
解析の結果、各種の間隙利用割合は昼間(30〜70%)が夜間(30%以下)よりも大きく、特にタモロコの利用が多いことが明らかになりました。また、各種ともある定位置間隙への経時的な定着性はほとんどみられませんでしたが、利用する間隙の位置には種特異性がみられました。すなわち、オイカワは昼には流心側の流れのある間隙を利用し、夜には表層の開放間隙に移動しました。タモロコは昼には底層の暗い閉鎖間隙を利用し、夜には水際の表層の流れのない間隙に移動しました。フナ属は昼間には流心側の深く流れのない暗い閉鎖間隙を利用しました(表1、図1)。
以上のように、魚種ごとに利用する間隙の位置には特徴がみられ、昼夜によっても利用場所が異なることが明らかとなりました。従って、多自然川づくりにおける環境ブロックや根固工は、多様な間隙環境が創出されるように設計、配置する必要があります。
担当:佐川 志朗、矢崎 博芳、秋野 淳一 |
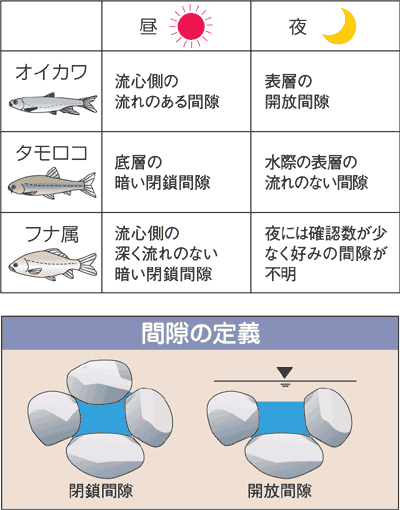 |
| ■表-1 石の間隙を利用する魚類の行動 |
 |
|
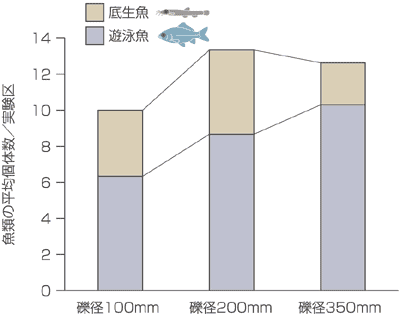 |
| ■図-1 魚種ごとの間隙利用状況 |
 |
|