|
● 背景と目的
ワンドは生物のホットスポットとして機能しており、稚仔魚や淡水二枚貝の生息場所として、流水環境の本川とは異なる生態系が成立していることが知られています。いままで我が国では、低水護岸を設置して直線化する河川改修が多く行われて来ましたが、そうすることで流速と水深が短調な環境だけが残り、ワンド域のような緩流域は消失し、そこに特徴的な生物も姿を消していきました。現在、多自然川づくりにおいてワンド造成は有効な修復工法としての可能性を秘めていますが、安易な造成については注意が必要です。本報告では名古屋市内を流下する直線改修河道で実施したワンド造成工事とその効果について紹介します。
● 方法
複断面直線河道(低水路幅:約30m)を呈する庄内川支流の矢田川において、右岸側の高水敷を縦断方向約100m(開口部距離)にわたり本川河床高まで掘り下げ、ワンドの造成を行いました(写真1)。また、事前調査において、本河川の河床材料は砂が卓越しており、わずかにみられる間隙(石の隙間)に魚類がよく生息していたことを鑑み、約30cm径の巨礫群を設置しました。さらに、河川全体にわたる平瀬環境を改善するために、水制工を用いてワンド上流部に瀬を創出しました。これらの修復工法が水生生物に対する影響を把握するために、水際部に8地点の調査地を設け、エレクトリックショッカーを用いて魚介類の捕獲を行いました。調査は工法導入前の2007年9月と導入後の2008年9月に行いました。
● 結果と考察
工法導入後、数回の中小出水を経て砂州が発達し(写真1)、7ヶ月後にはワンド上流部を閉塞するに至りました。水生生物は、2007年には13分類群1.6個体/m2確認されていたのに対して、2008年には、23分類群9.3個体/m2に増加しました。これらの増加にはアユやニゴイ等の在来種やコイ科稚仔魚の増加が大きく寄与しており、前者は瀬において、後者はワンドにおいて多く確認されました(図1)。しかし一方で外来種であるカダヤシの突出やブラックバスおよびブルーギルの定着も確認されました。これら外来種の出現場所はワンド域に集中しており、統計モデルを用いた解析からは、ワンド閉塞による流水環境の消失がこれらの定着に強く関わっていることが示唆されました。また、夏季には高水温、低溶存酸素の劣悪な滞留止水環境が成立しており、親水空間としても不適な状況がみられました。現在、庄内川河川事務所と協力して、以上を改善すべく流水もしくは伏流水確保のための試みを行っています。
担当:佐川 志朗、萱場 祐一、相川 隆生 |
 |
| ■写真−1 工法導入後半年が経過した施工地(ワンド造成区)の様子 |
|
| 導入前:流速が一様に単調であり、水生生物相が貧弱 |
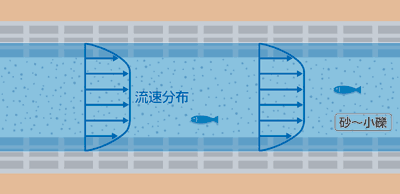 |
|
| 導入後:環境が多様になり、生息生物が増加 |
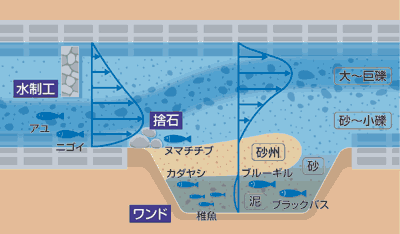 |
| ■図−1 導入前後の環境変化と定着種の分布状況 |
|