|
● 背景と目的
両生類、爬虫類および甲殻類の多くは、水域および陸域の両方を生息場所としています。このため、水域と陸域をつなぐ河岸は、これらの生物が移動しやすい形状である必要があります。そこで、河岸を利用する生物にとって、どのような河岸法面が登坂しやすいか明らかにするために、ヌマガエル、クサガメおよびサワガニを用いた登坂実験を行いました。
● 方法
河川で採取した砂利を、礫径75μm〜2mm(砂)、2〜4.75mm(細礫)、4.75〜53mm(中礫)、53〜256mm(大礫)に選別し、単一礫径をパネルの表面に埋め込み、凹凸の大きさが異なる4種類のパネルを作成しました。これらにコンクリート滑面を加えた5種類のパネルを河岸に見立てて本実験に用いました(図1)。
5種類のパネルの勾配をそれぞれ2割(約26.6度)、1割5分(約33.7度)、1割(45度)、5分(約63.4度)の4ケースに変化させて、計20パターンについて登坂実験を行いました。実験は、1パターンにつき各生物5個体ずつ行い、各パターンについて登坂成功率(%:100×成功個体数/5)を求めました。なお、登坂成功の定義は、実験開始後2分以内に、体の一部が法長40cmに達した場合としました。
● 結果と考察
ヌマガエルは砂・細礫・中礫による凹凸が登坂しやすく、勾配は登坂の可否には、影響しないことが分かりました(表1)。また、クサガメは細礫による凹凸と緩い勾配が登坂しやすく(表2)、サワガニでは中礫による凹凸と緩い勾配が登坂しやすいこと(表3)が分かりました。
以上により、河岸を利用する生物の種によって登坂しやすい河岸法面の条件は異なりますが、概ね、表面に凹凸があって、緩い勾配の河岸法面が登坂しやすいようです。このため、護岸を設計する際は、表面に凹凸を設けるとともに勾配を小さくすることが望ましいと考えられます。
また、生物によって登坂しやすい河岸の条件が異なる要因としては、各生物の登坂の方法(跳躍・匍匐等)や外部形態(爪や足のつくり)の違いが関係している可能性があります。このため、今後はこれらに着目し、実験方法を工夫して、生物が移動しやすい河岸の指標づくりを進めていきたいと考えています。
担当:上野 公彦、佐川 志朗、萱場 祐一 |
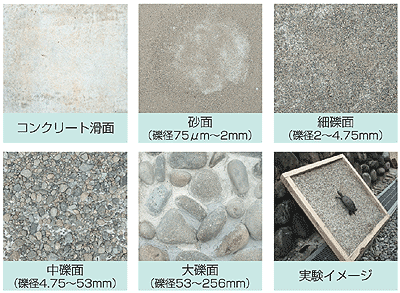 |
| ■図1 登坂実験用パネルおよび実験イメージ |
|
 |
| ■表1 ヌマガエルの登坂成功率(%) |
|
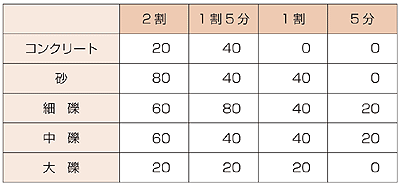 |
| ■表2 クサガメの登坂成功率(%) |
|
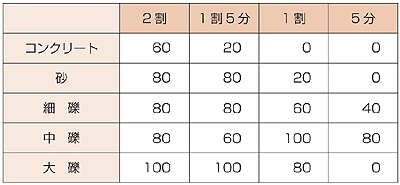 |
| ■表3 サワガニの登坂成功率(%) |
|
|