|
● 背景と目的
水域と陸域の中間的な環境要素を持つ氾濫原は、もっとも生物多様性が高い景観要素の一つであり、生物多様性保全の観点からも非常に重要です。氾濫原には、ワンドと呼ばれる池のような形状をした水域が形成されます。ワンドは、洪水時の増水により水が被ること(冠水)があり、形成された位置によって冠水する頻度が異なります。ワンド内の水環境はその影響を大きく受けることが知られています。このような性質を持つワンドは、淡水魚の生息場や摂餌場などとして重要な場所です。そこで本報告では、木曽川ワンド群の環境条件とそこに生息する淡水魚の多様性との関係について、特にワンドの冠水頻度に注目して明らかにすることを目的とした調査を行ったので紹介します。
● 方法
木曽川中流域に位置する冠水頻度が異なる3つのワンドタイプ(冠水頻度 高・中・低;図1)において各3ワンド、合計9ワンドで調査を行いました。平成21年2月にそれぞれのワンドに漁網(定置網3個と網モンドリ10個)を24時間設置して、魚類を定量採集しました。採集結果から、それぞれのワンドで種多様性の尺度である、種数とShannon-Wiener指数(H’;種数と個体数の両方が多いほど高い値になり、多様性が高いことを示す)を算出し、ワンドタイプ間で比較しました。
● 結果と考察
木曽川ワンド群では、7科19種合計1,895個体の魚類が採集されました。魚類群集の多様性(種数とH’)を冠水頻度が異なるワンドタイプ間で比較した結果、冠水頻度が低いほど魚類群集の多様性の低下が認められました(図2)。これは、冠水頻度が低いワンドほど、本流・ワンド間を魚類が移動する機会が制限され、ワンドに入ってくる魚の数が少ないことに加えて、水が滞留したことによって、ワンド内の溶存酸素濃度が夏場に低下し、低酸素に強い魚種(例えば、モツゴやドジョウなど)しか生き残ることができなかったことが原因と考えられます(図3)。今後、魚類の移動と冠水頻度との関係や生息条件を制限する生理的な要因の影響とその改善機構について、さらに詳しく解析する必要があります。そのことによって、今後の氾濫原における魚類群集やその生息環境の保全・再生に重要な知見を得ることができると考えられます。
担当:久米 学 |
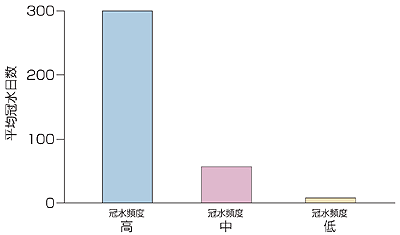 |
| ■図1 木曽川ワンドの冠水状況(日数) |
|
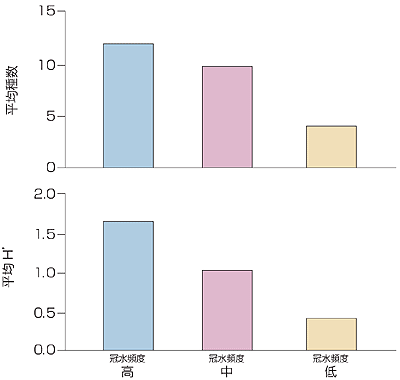 |
| ■図2 魚類群集の多様性(種数とH’)の比較 |
|
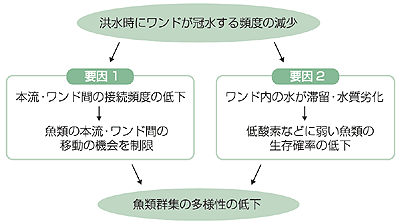 |
| ■図3 魚類群集の多様性が低下する要因に関する仮説 |
|
|