|
● 背景と目的
貯水ダムの多くは、ダム湖に水を貯めると同時に、土砂をその場で堰止めてしまいます。そのため、ダム湖に多くの土砂が堆積することで、貯水できる水量が減少するなど様々な問題が生じます。近年、この問題に対処するため、ダム湖の上下流をつなぐバイパスの建設が検討されています(図1)。これは、洪水時にダム湖へ運ばれる大量の土砂を、バイパスを通すことでダム湖を迂回させるものです。バイパスによって、ダム下流部に土砂を直接送り込むことが可能となり、問題となっていたダム湖への土砂堆積を未然に防ぐことができます。しかし、バイパスを通り、ダム下流部へ流れ出る土砂は、同時に河川水中の土砂濃度の上昇を引き起こし、濁水となって、ダム下流の生態系に様々な影響を及ぼす可能性があります。さらに、洪水時の流量は多く、土砂は非常に速いスピードでダム下流部を流れます。そこで、本研究では、ダム下流部で観察される非常に速い流速を再現可能な管路型回転水路を作成し、高濃度の濁水が付着藻類に及ぼす影響について検討しました。
● 方法
あらかじめ付着藻類を定着させたタイルを管路の中に入れ、平水時の流速を想定した0.5m/sと洪水時の流速を想定した4.0m/sの流速で水路内の水を回転させました。この水路内の水を三段階の土砂濃度に調整し(SS濃度:10mg/L、1000mg/L、10000mg/L)、24時間、水路を動かし続けました(写真1)。実験後、付着藻類に含まれている無機物量およびクロロフィルa量を測定しました。
● 結果と考察
土砂濃度(SS濃度)が高い濁水を流した水路ほど、付着藻類に含まれる無機物量は多くなっていました(図2)。一方、流速が遅いほど、無機物量の堆積が多くなっていましたが、これは流速が遅いほど土砂(無機物)が沈殿しやすいためと考えられます。一方、クロロフィルa量に対するSS濃度の影響は、流速によって違っていました。流速が遅い実験条件下では、クロロフィルa量に対してSS濃度は影響していませんでした。しかし、流速が速い条件下ではSS濃度が高いほどクロロフィルa量は多くなっていました。これは、付着藻類の表面を無機物が覆うように堆積したことで、速い流水による剥離を防いだためと考えられました。ただし、この無機物による剥離の防止は、付着藻類に到達する光量を減少させてしまうことが予想されるため、一次生産の極端な低下とその後に生じる付着藻類自体の劣化をもたらすことが予想されます。今後、一次生産の変化に焦点を当て、河川生態系にとって健全な濁水のあり方について検討していく予定です。
担当:森 照貴、小野田 幸生、萱場 祐一 |
 |
| ■写真1 実験で用いた管路を流れる各濃度の濁水 |
|
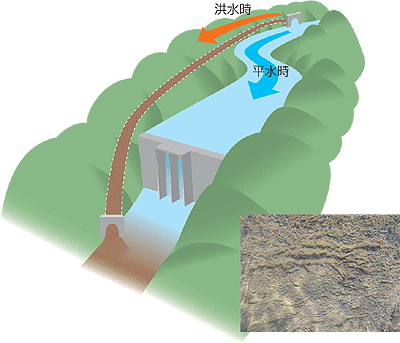 |
| ■図1 バイパス排砂の概念図(左)とダム下流部で観察される土砂の堆積した付着藻類(右) |
|
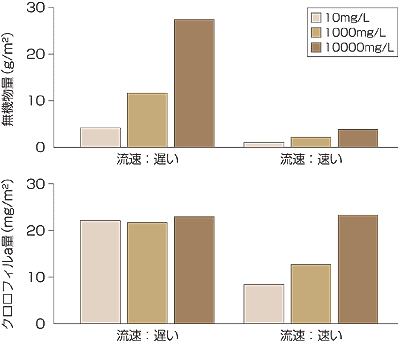 |
| ■図2 各濁水濃度条件下での付着藻類に含まれる無機物量(上)およびクロロフィルa量(下) |
 |
|