|
● 背景と目的
川が増水すると水に浸かる氾濫原内の水域は魚類にとって大切な棲家ですが、現在急速に失われています。一方で、本来は氾濫原の水域に依存して生活していたと考えられる魚類が、農業用の水路や水田を利用していることが知られています。しかし、現代的な圃場整備に伴う水路のコンクリート化や用水-水田-排水の分離が進むにつれ、水田や水路もまた魚類の棲家としての機能を失いつつあります。ここでは、調査地において水路を利用していた複数の魚類の生息条件から、農業用の水路が通年にわたる魚類生息場として機能するための水路環境について考察します。
● 方法
岐阜県関市の4地域12水路を調査対象としました。各水路に6~16mの調査サイトを2つずつ設定し、魚類の採捕、物理環境{水深、流速、河床材料、カバー率(河岸・水中植生の被覆率)}の測定を行いました。農業用の水路を通年の魚類生息場と考える場合、温暖で水量の豊富な灌漑期だけではなく、水量や水温が低下し、魚類の生存条件が厳しくなる非灌漑期(特に冬)も考慮しなければなりません。そこで、調査は灌漑期にあたる6月(春)と8月(夏)、そして非灌漑期にあたる9月(秋)と2月(冬)にわたって行いました。各季節で採捕された魚類の総生息量について、水路底が土砂の水路(土砂水路)とコンクリートの水路(コンクリート水路)との間で比較しました。また、優占種について、各季節で物理環境との関係を検討しました。
● 結果と考察
8月(夏)を除く3季節において、土砂水路における魚類の生息量はコンクリート水路よりも有意に高いことが分かりました(図1)。これは、少なくとも水路底が土砂で維持されていれば、農業用の水路が多くの魚類の通年にわたる生息場として機能することを示しています。8月に差が見られなかったのは、魚類の移動が活発なため、特定の水路環境への依存性が低下していたためと考えられます。温暖な時期(6月、8月、9月)において、優占種のうち4種は泥、砂、小礫のいずれかと正の関係性を示しましたが、寒冷な冬(2月)においては、4種がカバー率と、1種が水深と正の関係を示しました(図2)。以上のことから、農業用の水路が1年を通して多様な魚類の生息場として機能するためには、①水路底の土砂、②水際の植生、③特に非灌漑期における水深を維持するための水量が必要であることが分かりました。
担当:永山 滋也 |
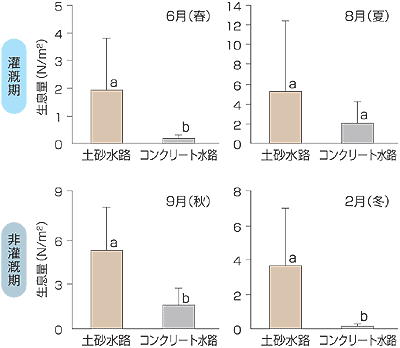 |
■図1 土砂水路とコンクリート水路における季節ごとの総魚類生息量の比較
(バーの上の異なる文字は統計的有意差があることを示す) |
 |
|
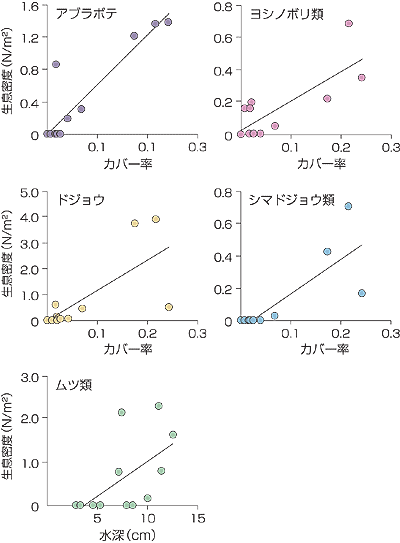 |
| ■図2 2月(冬)における優占種5種の生息量とカバー率もしくは水深との関係 |
 |
|