| 新潟試験所ニュース |
その後、土木研究所の組織は飛躍的に拡充され、それに伴って予算の伸びもめざましいものがあり、研究環境も次第に整備されてきました。新潟試験所においても昭和45年12月には低温実験室と道路融雪実験装置が完成しました。このように研究環境が着々と整備されていくなかで新潟試験所は創立10周年を迎え、昭和46年3月に記念式典とともに妙高村関山で雪崩制御砲による人工雪崩の公開実験も実施され、研究成果の一端が披露されました。 |
また、昭和48年3月には地すべりの基礎的研究を進めるための大型地すべり発生装置が設置され、地すべり現象解明に大きく貢献しました。 |
| (文責:清水) |
|
|
 |
| 新潟試験所職員全員集合です。よろしくお願いします。 飯田 内田 石田 服部 荒川 高橋 折野 阿部 清水 丸山 加藤 佐藤 早川 |

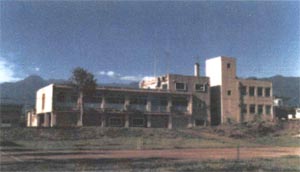
 去る10月2日にリンゴの木の栽培方法について勉強するため、長野県果樹試験場に行って来ました。
去る10月2日にリンゴの木の栽培方法について勉強するため、長野県果樹試験場に行って来ました。