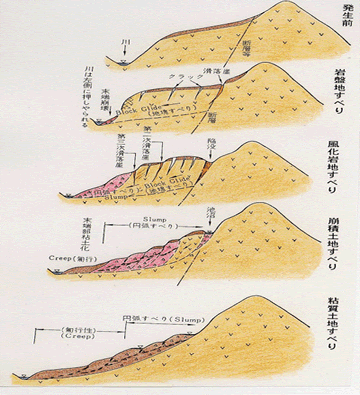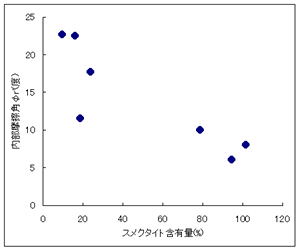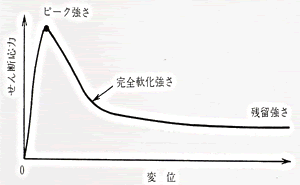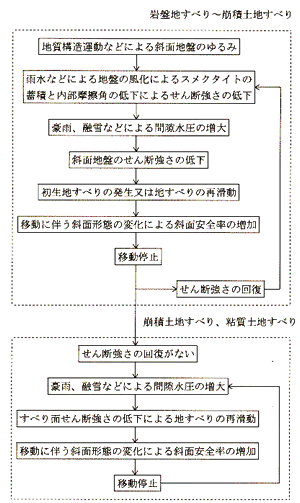| 新潟試験所ニュース |
第三紀層地すべりの発生機構
1.まえがき わが国は、国土の75%が山地であることや地質的に脆弱な地域が広く分布すること、豪雨や梅雨、融雪などの気象的に非常に厳しい条件下にあることなどから、地すべり災害が毎年多発しています。そこで、今回は、特に地すべり災害の多い地層である新第三紀層地帯(特に新潟、山形、長野、富山の泥岩が分布している地帯)に発生している第三紀層地すべりの発生機構について紹介します 2.地すべりの形分類と地すべり運動の継続性 図−1には、渡による地すべりの形分類を示しました。地すべりは、移動土塊の風化度により、岩盤地すべり、風化岩地すべり、崩積土地すべり、粘質土地すべりに分類されます。表−1は、渡による地すべりの形分類と地すべり運動の継続性について示したものです。地すべりは発生後も停止と滑動を繰り返し、形が変化して行きます。また、地すべりが滑動を繰り返す時間間隔(継続性)は、各形により異なります。岩盤地すべりでは突発的であり、風化岩地すべりではある程度断続的であり、崩積土地すべり及び粘質土地すべりでは断続的となります。 |
| 表-1 地すべりの形と運動の継続性(渡による) |
| 地すべりの形分類 | 地すべり運動の継続性 |
| 岩盤地すべり | 短期間突発的 |
| 風化岩地すべり | ある程度継続的(数十年〜数百年に一回) |
| 崩積土地すべり | 継続的(5〜20年に一回程度) |
| 粘質土地すべり | 継続的(1〜5年に一回程度) |
|
一般的な再滑動型地すべりの発生原因は、雨水や融雪水の地すべり斜面への地下浸透であり、その発生機構は、現地観測や実験により確認されています。しかしながら、このような地すべり発生機構は、長い場合数百年に一度単位で移動を繰り返す風化岩地すべり及び崩積土地すべりなどにはそのまま適用できません。その理由として、同じ気象条件の中で、粘質土地すべりは年単位で移動を繰り返すのに対して、風化岩地すべり及び崩積土地すべりは長い場合数百年に一度単位で移動を繰り返すことがあります。年単位で移動を繰り返す地すべりの移動は、地下水位の上昇によるすべり面のせん断強さの低下により生じますが、長い場合数百年に一度単位で移動を繰り返す地すべりの移動は、そのこと以上にすべり面のせん断強さが低下した場合にのみ生じることになります。このことから、後者の場合は、すべり面のせん断強さが低下する原因として、地下水位の上昇の他に、長期的なすべり面のせん断強さの低下について考える必要があります。 3.長期的なすべり面のせん断強度低下機構
長期的なすべり面及び地すべり土塊のせん断強度の低下機構として、以下に示すことが考えられます。 |
以上のことから、第三紀層地すべりでは、すべり面及び地すべり土塊のせん断強さの長期的低下機構として、地すべり移動にともなう物理的風化に よるすべり面粘 との関係(濱崎ほか)土の粘土含有量の増加や、空気中の酸素や二酸化炭素を含んだ雨水の地すべり斜面への地下浸透にともなう地すべり土塊の化学的風化によるスメクタイト量の増加などにより、すべり面及び地すべり土塊の内部摩擦角φ'が小さくなることが推察されます。また、再滑動型地すべりの発生機構として、短期的には地下水位の上昇によるせん断強さの低下などがあり、長期的には前述したようにすべり面粘土の内部摩擦角φ'が小さくなることがあると考えられます。 |
|
4.第三紀層地すべりの発生機構
第三紀層地すべりの発生機構を考える場合に必要なすべり面粘土のせん断特性として、前述したことの他に、以下に示すことがあります。 5.あとがき 第三紀層地すべりの発生機構について、最近の研究成果をもとに考察した結果を紹介しました。地すべり発生機構の解明は、地すべり防止の基本となるものです。新潟試験所では、今後も地すべり発生機構について研究を進めて行く計画です。 |
| (文責:丸山) |