| 雪崩・地すべり研究センターたより |
|
||
| 中越地震から一年 ‐積極的研究活動‐ 平成16年10月の中越地震は、地震計による観測が始まって以来初めて記録した震度7をはじめ6強など激烈な地震が連続して発生し、約3,800個所で崩壊土砂量の合計約1億立方メートルといわれる斜面崩壊が瞬時に発生しました。多発した斜面災害のうちでも特に地すべり災害は、1年間の日本中で発生する全個所に匹敵する131箇所で発生し、大規模な地すべり土塊の滑動により、集落直撃、アクセス道路及びライフラインの寸断、河道閉塞などが多発し、今でも9千人近くが未だ避難中であるように長期にわたる集落孤立化は、中山間地の存続に関わるなど深刻な影響をもたらしています。
|
||
|
||
| 夏期実習生として9月1日から22日まで、土木研究所にお世話になりました。私一人きりで不安で、実習が始まる前日の夜はあまり眠れないほどでしたが自分に与えられた机やパソコンを見て、非常な喜びを感じました。実習の間は、数多くの雪崩や地すべりの現場や、災害対策の施設など、普段行くことのない山奥や工事現場を調査でき、とても良い経験になりました。 またデスク作業で自分の収集したデータが、これからの研究に生かされると思うととてもうれしいです。 福井大学工学部建築建設工学科三年 若林佳枝
|
||
|
||
|


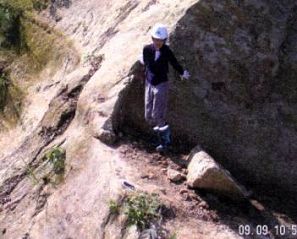
 昨年のこの時期は、赤々と実ったリンゴをカラスに味見をされないように心配していたのですが、今年は、30個ほどしか実を付けませんでした。現在、リンゴは4個なっていますが、虫食いや鳥につつかれてしまい、残念ながら収穫はゼロとなりそうです。13年目を迎えた木は、樹高約6m、下枝の長さ最大で9mと一段と大きくなりました。来年は今年の分も実をならすべく今から樹木の手入れに励んでいます。
昨年のこの時期は、赤々と実ったリンゴをカラスに味見をされないように心配していたのですが、今年は、30個ほどしか実を付けませんでした。現在、リンゴは4個なっていますが、虫食いや鳥につつかれてしまい、残念ながら収穫はゼロとなりそうです。13年目を迎えた木は、樹高約6m、下枝の長さ最大で9mと一段と大きくなりました。来年は今年の分も実をならすべく今から樹木の手入れに励んでいます。