 |
| 写真1.講演会の様子 |
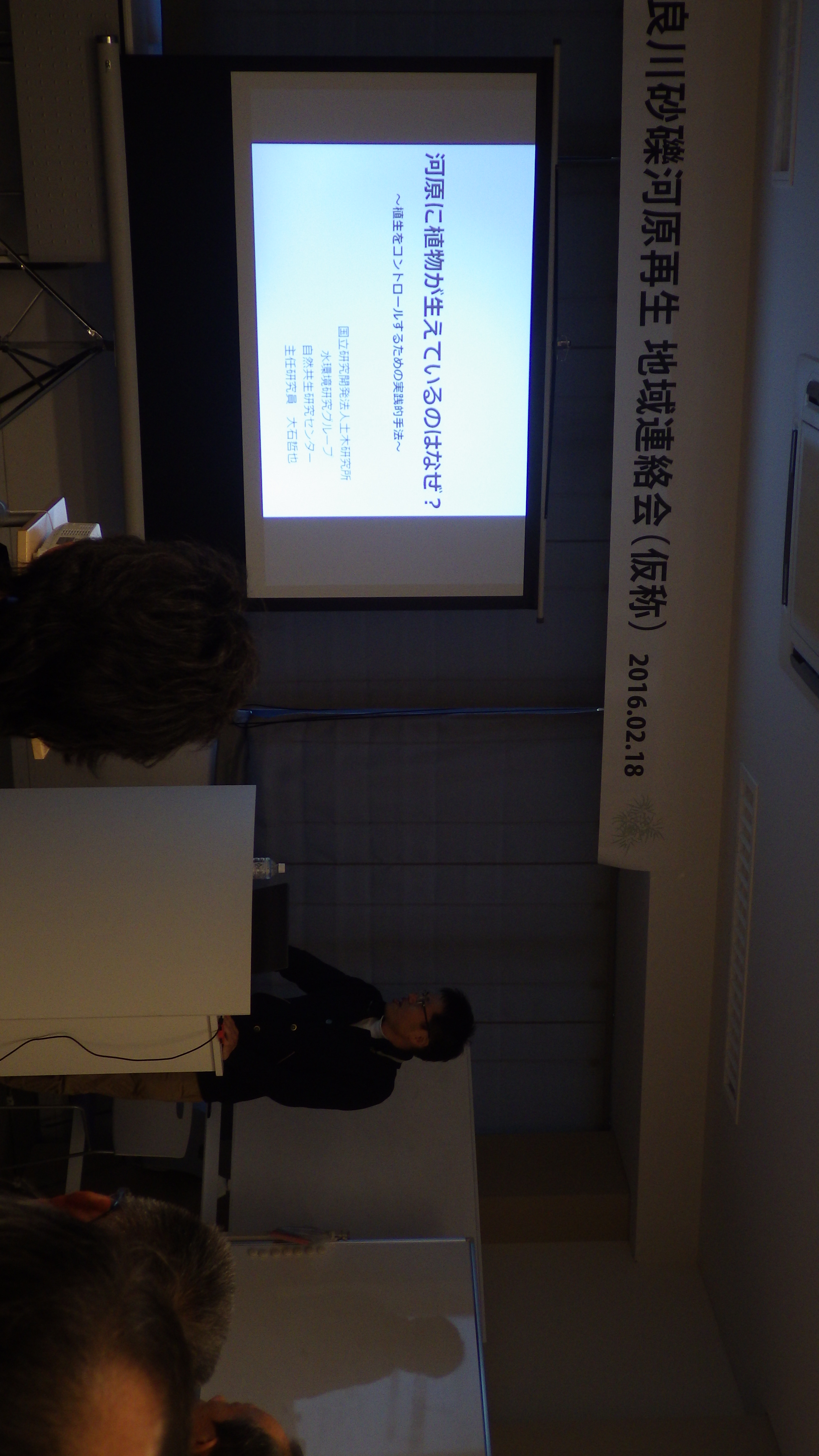 |
| 写真2.大石主任研究員による講演 |
 |
| 写真3.意見交換会での様子 |
|
長良川砂礫河原再生 地域連絡会(仮称)で「植生をコントロールするための実践的手法」に関する講演が行われました。
2016年2月18日に、長良川砂礫河原再生に関する地域連絡会が長良川うかいミュージアム会議室で行われました。
学習会では、当センターの大石哲也主任研究員による「河原に植物が生えているのはなぜ?〜植生をコントロールするための実践的手法〜」と題した講演がありました。その中で、河原に植物が生えるのは、植物の制限要因である光、水、温度などが水位変動や土砂輸送を通じて影響を受けた結果であることが、野外調査や実験の結果を織り交ぜながら解説されました。たとえば、河原には多くの種類の種子が埋まっているという調査結果が紹介され、発芽の可能性を決定する物理環境が、河川植生に対して支配的と考えられることが説明されました。
また、その発芽が土壌構造(礫の厚さや砂の多さ)や水分によって影響されるという実験結果も紹介され、河原の植物管理の中で地形条件を考慮する重要性が解説されました。講演後には、流域の土砂生産と河原の植物との関連についての質問等があり、活発な議論が交わされました。
その後の意見交換会では、今回の学習会やこれまで実施されてきた長良川における河原再生を踏まえて、現在の問題点や今後の河原の目標像などについて、いろいろな立場の方が自由に意見を交わしました。個人的に印象的だったのは、河原が河川の健全性のバロメーターの一つになるのではないかという広い視点での意見に集約されたことでした。また、河原の植物も含めた再生を考える際には、流域スケールの水や土砂を調整するという「原因療法」の重要性も理解しつつも、河原の植物の間引きなどの「対症療法」などもできる範囲で実施していくべきではないかという、現実的な意見も出されました。参加者全員が真剣に取り組み、地元の誇りである長良川を、後世に受け継いでいきたいという切実な思いを感じる時間でした。
(文責:小野田幸生)
|