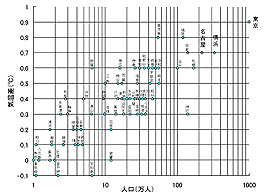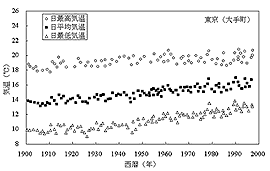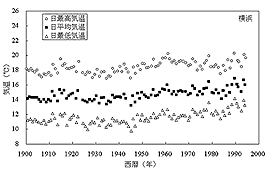|
都市気候の現状
都市の中心部が高温化し、熱の島のように見えるヒートアイランド現象は、日本のみならず、先進国の諸都市で確認されています。我が国の諸都市のヒートアイランド化について、浅井(1996)は1961年から1990年の年平均気温平年値と1931年から1960年までの年平均気温平年値の差を取り、1990年の人口との関係を整理しています(図-1)。これによると、多くの都市で人口の対数に比例して、統計上、気温の上昇が見られます。また、東京、横浜の過去約100年間の気温変化をみると、1950年代以降、最低気温が顕著に上昇していることがわかります(図-2)。夏期だけに限ってみても、東京で熱帯夜(最低気温が25℃以上の場合)の日数が1960年代には年平均14.6日であったのですが、1988〜97年では年平均日数が24.6日に、1991〜2000年では29.6日に増大にしています(朝日新聞,1998,2001)。このような増大傾向は他の都市にも見られます(表-1)。
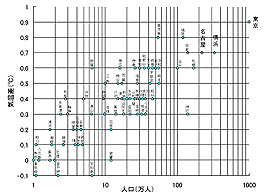
図-1 各都市の人口と気温差の関係
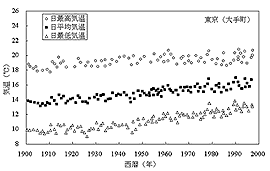
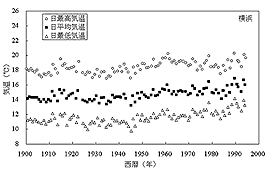
図-2 東京と横浜における日最高気温、日平均気温、日最低気温の経年変化
表-1 熱帯夜の年平均日数の変化
| |
仙台 |
東京 |
前橋 |
甲府 |
名古屋 |
京都 |
広島 |
松山 |
福岡 |
| 1931〜40年 |
0 |
7.0 |
0.3 |
- |
0.7 |
1.7 |
- |
2.3 |
6.5 |
| 1960年代 |
0.2 |
14.6 |
0.9 |
0.4 |
5.9 |
9.5 |
11.4 |
- |
20.7 |
| 1988〜97年 |
1.4 |
24.6 |
5.8 |
4.5 |
17.1 |
18.7 |
26.3 |
- |
30.8 |
| 1991〜00年 |
1.5 |
29.6 |
6.3 |
- |
19.6 |
23.2 |
- |
19.8 |
33.7 |
都市と郊外の気温差(ヒートアイランド強度)と人口や都市構造との関係についても報告がなされています。河村(1977)は3月の静穏晴天時の観測結果から、東京ではヒートアイランド強度が最大10℃にも達していることを明らかにしています。福岡(1983)は都市内外における最大気温差と都市全体における水面・緑地・畑地の面積率との関係を整理しています。それによると,水面等の面積率が小さいほど最大気温差が大きくなる傾向が見られますが、水面等の面積率が3割以上では最大気温差にそれほどの違いがなくなることを示しています。この結果には都市の地理・地形条件や産業、運輸等に起因する人工排熱などの影響が含まれています。
都市の高温化はそれ自体が生活環境を悪化させるとともに、副次的な影響をもたらします。暑い夏における熱ストレスの健康影響に関する調査結果によると、日最高気温が33℃以上になると死亡率が増大傾向になること、日最高気温が31℃を超えると熱中症患者数が指数的に増加することが報告されています(西岡・原沢,1997;Ando
et al.,1997)。佐藤・高橋(2000)はアメダスの降水データの分析から、都市の高温化が誘因となって夏の降雨特性に変化が起こり、東京都区部や横浜では激しい雨の割合が増加している可能性が高いと指摘しています。神田ほか(2000)は数値計算に基づき都市化と人工排熱が都市上空の積雲の雲量増加をもたらすことを示しています。夏季の都市高温化は冷房需要の増大を招き、電力消費量を押し上げることとなります。電力10社合成の夏期最大電力の気温感応度(気温が1℃変化することによる最大電力消費の変動量)は、1990年度には約340万kW/℃であったのに対して、1999年7月、8月の平日データから算出される値は約490万kW/℃となっており、年々増加しています(建設省都市局,1999)。これにより化石燃料消費量と二酸化炭素排出量がともに増大して、地球温暖化を助長するおそれがあります。冬期には逆に高温化が燃料消費を抑制しますが、電力消費で見ると1999年冬期の気温感応度は170万kW/℃と夏期に比べて小さくなっています。
|