|
体感指標とは
体感指標とは人間の暑さ、寒さの感覚(温冷感覚)を表す指標で、多様な気象条件における温冷感覚を単一の尺度で表すことができます。体感指標を用いれば、気象予報と連動させて日々の温冷感予測が可能となるし、ヒートアイランド対策が温冷感覚にどのような変化をもたらすかの推定に利用することもできます。
体感指標は、従来、空調分野や気象分野で研究されてきており、様々な指標が考案されています。それらほとんどは屋外への適用性の検証がなされていないものや限定的な気象条件で利用できるもので、屋外空間の様々な気象条件下、特に夏期と冬期の厳しい気象条件での温冷感を精度良く評価できる指標はまだ確立されていないのが実態です。
屋内空間の温冷感覚評価に関しては、ASHRAE(米国暖房・冷房・空気調和学会)の標準となっている標準有効温度SET*(Standard
Effective Temperature)やISOの基準として制定されているPMV(Predicted Mean Vote)が用いられています。SET*やPMVは、気温、湿度の他に日射や風の影響、人間の着衣状態や作業状態も考慮した物理的、生理的理論に基づく指標であり、原理的には屋外空間への適用が可能であると考えられますが、それぞれの指標が作成されたときの条件に制約があります。SET*は人体の深部層と皮膚層の2層モデルにより表現した熱平衡方程式に基づく体感指標です。このモデルでは、図-1に模式的に示すように、人体の代謝熱量Mと人体から大気への潜熱輸送E+Eres(皮膚から衣服を通じての不感蒸泄と発汗、呼吸による蒸発)、顕熱輸送C+Cres(衣服-大気間の顕熱輸送量、呼吸による顕熱輸送量)、衣服から大気への赤外放射R、大気や周囲から受ける放射r、外部に対してなした仕事Wとの釣り合いを求めており、皮膚血流、発汗、ふるえによる体温調節が組み込まれています。しかしながら、暑い環境では生理反応(発汗)のモデル化に実際とのずれが生じることが指摘されています。また、PMVでは相対湿度が温冷感覚に与える影響を加味しておらず、PMVの基礎となった実験条件も無風、気温19.9〜27.8℃の範囲でしかありません。
SET*の他に、人体の熱収支解析に基づく体感指標として仮想熱負荷量VTLがあります。VTL算出に用いられるモデルは人体を単一層として扱っており、着衣・作業状態と人体の発汗作用を考慮しています。
SET*同様、数値プログラムを利用する必要があり、屋外空間への適用性については若干の検討が試みられています。
気象学分野では米国気象局が作成した不快指数THIや米国で冬期に利用されている風力冷却指数WCI(Wind Chill Index)があります。不快指数は算定式の簡便さから、我が国でも夏期の気象状況を表す指標として一般に用いられているものの、気温と湿度のみからなる評価式のため、屋外空間の熱環境の特徴である日射や風の影響が考慮されていません。また、風力冷却指数は極寒状態において人体から失われる熱量を簡易な式で指標化したもので、風速の適用条件が限られており、微風時、放射による冷却が卓越する場合への適用性については検証が必要です。
屋外では放射、風の影響が大きくなることを考慮して提案された温冷感指数TSIは夏期、冬期の幅広い屋外の気象条件に適用できるように求められた次の簡易指標であらわされます。
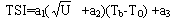
ここで、To:作用温度( = ( hrTr + hcTa )/h )、Tb:基準温度(=36.8℃)、対流熱伝達率 、放射熱伝達率は夏期と冬期の平均的な値としてhr=6.12(Wm-2K-1)及び4.81(Wm-2K-1)を用います。a1、a2、a3は実測値に基づき求められる定数で、夏期はそれぞれ0.158、0.19、3.59、冬期はそれぞれ-0.025、2.0、4.19としました。現地における放射温度Trを算出するには短波放射量と長波放射量の直接測定結果から計算する方法と、グローブ温度計を用いる方法があります。後者の方が必要な機器も少なく、簡便にTr(すなわち正味の入力放射量)を推定できるが、どのような放射成分の寄与が大きいかまではわかりません。
以下、夏期と冬期の双方に適用できる屋外空間の温冷感予測指標として、人体熱収支解析に基づくSET*及び簡便な式に基づき温冷感を直接推定する温冷感指標TSIを用いて、現地への適用性を比較します。
|

