|
様々な対策の効果を推定するシミュレーションモデル
本研究で用いたシミュレーションモデルは、米国ペンシルバニア州立大学で汎用の気象計算モデルとして開発され(Anthes
and Warner, 1978)、その後、NCAR(米国大気研究センター)においてさらに改良されたMM5(The fifth-generation
Penn State/NCAR mesoscale model)を基本にしています。今回、MM5を直接我が国のヒートアイランド解析に用いるには不都合な点がいくつか挙げられます。そこで、以下に示すような改良を加えました。
(1) サブグリッドスケールのモデリング
MM5では各計算格子には卓越する1つの土地利用のみを与えているため、我が国の都市のような複雑な土地利用形態に適用する場合や計算メッシュサイズが大きい場合には、サブグリッド規模の一様性の仮定が成り立たず、地表面からのフラックス輸送量の算定結果に大きな違いが生じることが予想されました。そこで、複雑な都市の土地利用に適した地表面フラックスの算定ができるようにサブグリッドスケールのパラメータ化手法(Avissar
and Pielke, 1989;Kimura, 1989)を導入しました。
(2) 土地利用情報
土地利用情報として国土地理院が整備・発行する国土数値情報(KS-200-1,土地利用分類ごとの面積率データを使用)と細密数値情報(首都圏1994年版,解像度10m)を使用できるようにしました。標高情報については国土地理院の数値地図(250mメッシュデータ)を用いました。土地利用は国土数値情報と細密数値情報の分類を13分類に集約しました。
(3) 地表面モデルの改良
蒸発効率は土壌水分量に強く依存することから、潜熱輸送量の日変動をより精度よく再現しようとするならば、地表面モデルにより土壌水分量を推定するのが望ましいと考えられます。そこで、今回MM5の境界層モデルにNoilhan
and Planton(1989)の地表面モデル(地表面の水分移動モデルと植物生理のモデル)を新たに組み込んで、地表面水分量の変化を予測し、地表面の水分量に応じた植生面からの蒸散量や裸地面からの蒸発量の算出ができるようにしました。
(4) 人工排熱
都市のヒートアイランド形成の大きな原因のひとつは社会経済活動によって発生する人工排熱です。オリジナルのMM5では人工排熱を考慮していないため、接地層に土地利用分類や時間に応じた量の人工排熱を潜熱と顕熱のフラックスの形で与えられるようにモデルを修正しました。
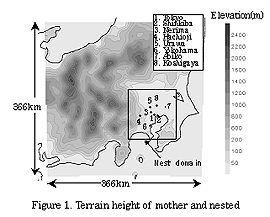
図ー1 Terrain height of mother and nested
(5) 都市キャノピー
都市キャノピー層の存在は大気下層の熱輸送や放射環境に大きく影響を及ぼすと考えられますが、人工排熱と同様にMM5ではこれを考慮していません。ここでは、長波放射のみ都市キャノピーの影響をパラメータ化する簡易なモデルを作成しました。
検討対象域
東京都心部を中心とする首都圏を対象に、シミュレーションモデルの計算精度を検しました。計算対象領域は関東平野を含む366km四方の母領域(領域1)と東京23区を含む114km四方のネスト領域(領域2)です(図-1)。領域1の解像度は6km、計算メッシュ数は61×61、領域2は2km、57×57としました。鉛直方向は100hPaの等圧面までを25層に分割しました。この場合、モデル最下層の厚さはおよそ15mとなります。領域1の初期条件、境界条件には計算対象日を含むNMC
(National Meteorological Center)の全球解析データを用いました。
表-3 各物理モデルの概要
| 基礎方程式 |
Three-dimensional non-hydrostatic dynamics |
| 境界層モデル |
Mellor and Yamada closure model level 2.5 (Janjic,
1990, 1994) |
| 雲モデル |
None |
| 放射モデル |
Simple cooling |
| ネスティング |
Two way |
| 境界・初期条件 |
NMC global analysis |
| 地表面モデル |
Noilhan Planton Model, six-layer soil model,
Subgrid parameterization |
|

