|
河川の効果(広島での事例)
河川が気温を調節する作用については既にいくつかの研究が存在し、現地調査結果に基づく詳細な分析が行われています。しかし、夏期の海陸風出現時を対象として、市街地スケールで気温以外の要素も含めて面的に気象の特徴を捉えるという試みは極めて少ない状況です。都市スケールにおける水面や緑の効果をシミュレーションにより明らかにする上でも、市街地スケールでの現象の把握と理解が必要です。そこで、太田川が流れる広島市街地において実施した現地調査データを分析し、市街地スケールにおいて河川が気温や風の場に及ぼす効果を明らかにしました。
地上の風向・風速の測定結果
図-1〜4に8月9日と11日の各測定地点における風速、風向の平面図を示します。海よりの風が吹いていた9日と11日の14時では河川上で強い風が見られるとともに、河川から周辺市街地に吹き込む風も確認できます。一方、陸風の吹く11日19時の場合には、河川上とそれ以外の地点における風速の違いは顕著ではありません。
図-5は8月11日14時における気温の等高線と風向・風速の平面分布を表したものです。成田(1987)が既に指摘しているように、河川の存在により、都市の中心部から周囲に同心円状に広がるヒートアイランドは見られず、いくつかに分断されている状況がとらえられています。また、同じ河川沿いであっても、河川の線形や河川に直交する街路の大きさに応じて、場所場所で気温に違いが生じている様子や、河川を横断する方向に見た場合に川と川とで挟まれる市街地部分が広いエリアで33℃以上の気温が生じていることが読み取れます。
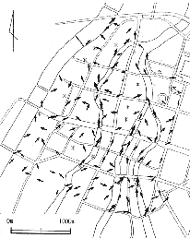 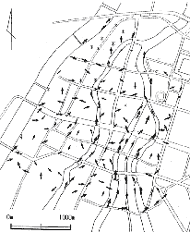
図-1 (8月9日14時) 図-2 (8月9日19時)
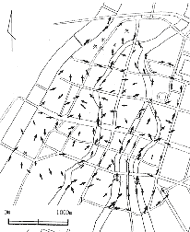 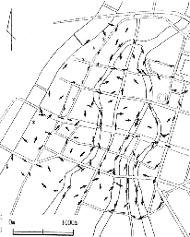
図-3 (8月11日14時) 図-4 (8月11日19時)
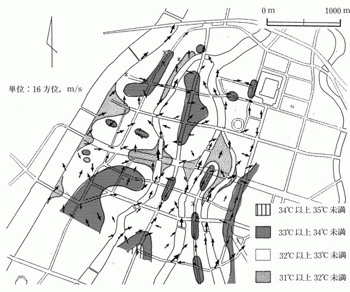
図-5 気温と風向・風速の平面分布(8月11日14時)
気温の分布および気温と風速の関係
図-6〜9には各地点の風速と気温の関係を地点種別に示します。9日、11日の両日とも、日中は河川上の測定点で気温が相対的に低い値を示しており、広島湾からの冷風があまり加熱されずに侵入してきているものと推定されます。河川沿いと堤内地を比較してみると、わずかに河川沿いの地点での気温が低い傾向はみられるものの、堤内地の方が河川沿いよりも気温が低い地点もかなり見受けられます。9日の19時の測定では堤内地と河川沿いの地点における気温の違いが日中よりも明瞭になっています。測定域上空では日中、陸面に対する境界層が発達過程にあると考えられることから、内陸に行くほど地上の風速も弱められ、海風の吹送に伴う累積の大気加熱量も多くなると考えられます。このため、風速が大きい地点で気温も低く、逆に風速が小さくなると気温も上昇する傾向が現れたものと考えられます。しかし、夜間にはそのような傾向は認められませんでした。

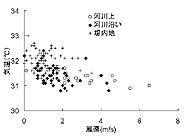
図-6 風速と気温の関係(8月9日14時) 図-7 風速と気温の関係(8月9日19時)
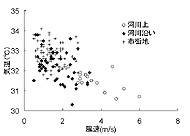 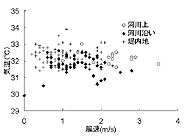
図-8 風速と気温の関係(8月11日14時) 図-9 風速と気温の関係(8月11日19時)
|

