 |
| 1.熱心に講演される谷口先生。50年に及ぶ詳細なデータに基づき、種の取り除きや侵入によるウィンターグリーン湖での個体数の増減とその要因について分かりやすく説明して頂きました。
|
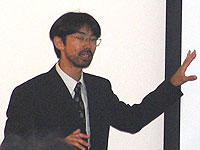 |
| 2.前半は自然科学的観点から生物相互関係に関する講演、後半は米国のスポーツフィッシングを巡る考え方と様々な規制や制度を、歴史を紐解きながら講演して頂きました。研究成果だけでなく社会制度そのものの違いに淡水魚の保全のポイントが隠されているようです。
|
 |
| 3.種の再移植により群集構造は本当に元に戻るのか? 米国の研究や制度から日本は何を学べるのか? 等会場から様々な質問が飛び、谷口先生とのディスカッションが行われました。
|
|
講師は山口県立大学 谷口 義則 氏
前半:ブラックバスとブルーギルの絶滅と再移植が湖の生態系にもたらす影響:50年間の個体群変動から学ぶ
後半:北米の遊漁管理について ―日本の河川・湖沼の保全のために―
2005年5月9日、山口県立大学の谷口義則助教授をお招きして、魚類の保全と管理に関する講演会を開催しました。
講演会は前半と後半に分かれ、前半は米国ミシガン州ウィンターグリーン湖における長期間に及ぶ群集動態を、後半は米国におけるスポーツフィッシングを巡る考え方や法規制、制度について解説して頂きました。群集動態は、ブラックバスが移植されることにより、シャイナーが捕食され絶滅したこと、シャイナーの餌である動物プランクトンを媒介として他の種が影響を受け個体数が変化したこと等が紹介されました。
後半は北米の遊漁管理が、魚と生息場所そして人間が相互に関連しながら実施されていること、特に遊漁に関するPRや環境教育が適切な遊漁管理を行う上で重要なファクターであることが紹介されました。
|