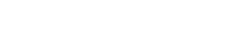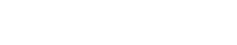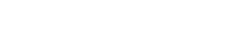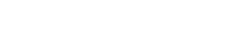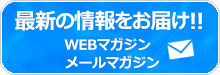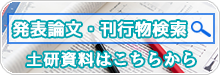年頭のご挨拶

新たな年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
昨年は、まさに年初に令和6年能登半島地震が、7月には秋田県、山形県を中心とした大雨が、そして9月には1月の地震による打撃を受けたエリアに重なるように 奥能登豪雨が発生し、大きな災害となりました。あらためまして、災害により亡くなられた方に対し、謹んで哀悼の意を表します。そして、被災地域の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
土木研究所は、新たなこの1年を、災害を受けにくい、災害を受けても立ち直りやすい国土・地域にするための土木技術を高め普及することを引き続き柱の一つにしつつ、次のような抱負をもって歩んで参ります。
1つ目は、
「今もこれからも土木技術の本質をしっかりとらえることを常に意識する」ことです。
土木研究所の任務は「土木技術の向上」を通じて『世の中を良くする』ことです。 人間社会が持続的に発展でき、自然の恵みを享受しながら、誰もが・どこでも注)・安心して生き生きと暮らせる社会の実現に向けて、
地球と人間との間に“インターフェース” を備える-これはまさにインフラストラクチャーであり、その構築は、文明が始まって以来 今日に至るまで人類の営為となってきました。この「良くなる」 ための機能が
国土そして各地域で永らく発揮されるようインフラ群を上手につくり、なじませ、手入れをする-その根幹にあるのが土木技術です。インフラ整備は必須の手段ですが、その前提には「世の中を良くする」という大目的の実現があるのです。
注)インフラへの素朴な希求の1つであった「どこでも」は、今日、「それぞれの土地の自然や地理をよく理解した上での思慮深い巧みな国土の使い方を地域本位で追求しながら」に昇華していく。
2つ目は、 「土木研究所の心棒を自覚し、それを日々の取り組みの基とする」ことです。私たちが一貫して大切にしてきているのは、次の6つです。
1. 現象・課題・ニーズの本質を追究する。現象理解に際しては科学的思考を通徹する。 →これこそが問題解決、改善、ブレークスルーの本道である。 2. 獲得知見の体系化と幅広い共有化、開かれた専門的議論を通じた切磋琢磨を怠らない。 3. 実際」を尊重する。 →理論や解析は本質的手立てであるが、あくまで“主人”は現実・現場であり、逆ではない。理念、概念もしかり。 4. 新しい知見や技術が現場実装される仕組み(土木技術と社会との関係性を含む)への理解力を持ち、現場実装まで完遂することを重視する。 5. 必要であれば、不完全情報下でも合理的総合判断や見解を根拠とともに示す。 →“わからないこと”から逃げずに直視し、対象を、 “きれいにわかりそう”だから選ぶのでなく、必要だからこそ選ぶ。 6. 研究開発成果の適用、技術適用、技術判断について深い責任意識を持つ。 →適用や判断が、真に、それを受ける相手方の ためになるよう最善を尽くす(自分たちの名声を上げることは目的ではない)。この根底には、土木技術の存在が、そして土木研究所の任務が、本源的に「公益」に資するもの、「利他的・倫理的・公共的」であることがある。
3つ目は、 「確固たる土台に、時代の要請を自ら考えて注入する」ことです。 土木技術の本質と重要性は揺るぎません。しかし追求する対象も実現の手段・道筋も時代とともに変わります。土木研究所も、その心棒を堅持しつつ、なすべきことをそのつど洞察し、自らのあり方と仕事の内容・やり方を開拓して来ました。 現下の取り組みの中軸は、直面する自然災害の激甚化・頻発化、膨大なインフラの老朽化進行、急速な生産年齢人口の減少、気候変動影響への対処をターゲットとした「第5期中長期計画」です。 本年で6年間のうち4年目を迎えます。その実施においては、既存技術を伸ばす一方、時にその“天井”を突破し、 新興著しい技術の組み込みと分野間の越境・融合を積極的に図り、 従来思考・枠組みにとらわれず目標達成本位に進んでいきます。3年前に作られたこの計画を、固定的に捉えるのではなく、研究の進展によっては、さらにダイナミックに良い成果を産み出す発射台とも捉えます。 冒頭にもあるとおり、自然災害は激甚化・頻発化しています。私たちは、災害が起きてしまった時には、まず、現場に対して迅速・的確な技術支援を行い、復旧に技術面で貢献すべく、打撃を受けた現場の状況を 見据えて求められる技術力を発揮すべく、全力を尽くします。その際には、技術の蓄積に培われた深い専門知識に基づく洞察と感情に左右されない理を(しかし心根には熱さを)もって総合力を発揮することが重要となります。 そのために、日々の研究や調査の中でも現場に足を運び、現場と対話を重ねることで、「実際」を的確に理解できる力をつけるようつとめています。次の災害に備えることも含め、世の中をよりよくするための土木技術の研究・ 開発において何が重要か、土木研究所の職員すべてが一体となって考え、試行錯誤しながら、私たちは前進し続けます。
4つ目は、 「未来へ繋ぐ『動力』を創出する。」ことです。 困難な課題を様々に抱える我が国において、国立研究開発法人(国研)には、産学官連携によるオープンイノベーションを推進し、国家的重要課題に戦略的に対応することが求められています。 このことは、令和6年3月に発出された関係府省申合せである「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」においても、明確に位置付けられています。 土木研究所は、SIPの研究推進法人、SBIRの運営支援法人をはじめ、産学官ネットワークの「ピボット」としての役割を担い、イノベーションの“回転”を促進し、成果の社会実装を促進することに貢献しています。 また、土木分野における「ピボット」の機能を確保する上で、国土交通省をはじめとするインフラ整備の現場との密接な“接続”は基本中の基本となります。 この“回転”、”接続”を行うための『動力』は、拠点となる土木研究所の人材、それを育てる制度、整備された環境です。私たちは、これらの育成と整備も着実に進めます。
5つ目は、 「“遊び” が生む新たな可能性を模索する」ことです。 時代の変化や新たなニーズに対応するために、異分野や他機関との連携を積極的に図ることが不可欠であることにここまで触れてきました。 その過程で重要となるのが、個々の研究者などが能動的・自発的に発する、好奇心に根ざした“遊び”の精神です。 ここでいう“遊び”とは、その時は本筋から離れたとも見える視点で、「こんなこともできるのではないか?」「この技術を取り入れるとこういう新たな可能性が広がるのではないか?」 「面白そうだからちょっとやってみよう」といった自由な発想を持つことを指します。一見土木技術と関係なさそうな分野の応用が、私たちの研究に新しい地平を切り開くこともあります。 そして、このような“遊び”の中から生まれるひらめきが、のちのち本筋をより豊かにすることも珍しくありません。実は、この5つ目は、所内の若手(私から見て)から書いてほしいと 特に突き上げられたところです。結果、ここに入れるべしと私自身が考えた次第です。 来る1月23日には、SATテクノロジー・ショーケース2025がつくば国際会議場で開催されます。 これは、つくばをはじめ首都圏で活躍する研究者・技術者が、最新の研究成果、アイディア、技術を持ち寄り、相互に披露する異分野交流による知の触発を企図した催しです- いわば、最新研究・技術の“フリーマーケット”!(決して不用品ではないですが)。今回は、私たち土木研究所が企画担当をさせていただいていることもあり, インフラ × ○○?! 最先端技術が創るよりよい未来 がテーマとなっています。このテーマの下での特別シンポジウムもあります。大学生など次代を長く担うであろう人たちからも多くの参加をいただいています。 「×(掛ける) ○○」に込めたことは次のようです。○○は、すなわちインフラづくりを担うのは、もはや、狭義の土木技術だけではない。今までは無関係と思われていた分野も含め、 広範な知の交わりと融合がインフラを、ひいては世の中をぐんと良くしていく。そのような展開への一つのきっかけにしたい、と言うことです。この趣旨にご興味のある方は是非のぞいていただきたいと思います。 ※ SATテクノロジー・ショーケース2025はこちら 以上、今年1年間の抱負を述べました。いずれにおいても大事なのは「人」です。どんなに優れた環境、設備、豊富なリソース等を整えたとしても、それを真に活かし、価値あるものを生み出すのは「人」です。 「人」---これを大事にする。ありきたりではありますが、このことを心に刻み、常に問いかけ続け、結果として土木研究所全体が発展し、世の中に大きなインパクトを与える存在になっていくことを目指して 行きたいと考えています。今後とも、共に未来を切り拓くパートナーとして、どうぞご支援賜りますようお願い申し上げます。
令和7年1月
国立研究開発法人土木研究所
理事長 藤田 光一